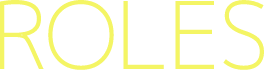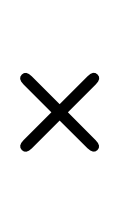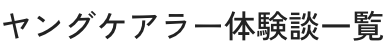#1 ケアの始まり(友田智佳恵さん) 12歳のとき、突如として始まった大好きな母のケア。友田智佳恵さんが語る自身がヤングケアラーとなった“あの日”。
2024.01.26
“だから皆、私と会うと元々こういうね、元気な、 ポジティブな人間なんだって思うらしい。でも、ずっとそうだったわけじゃないし、やっぱりいろんな葛藤とか、向き合いの中で、今の自分がいるっていう感じ。本当にそう。”
自分の胸の内を、真っ直ぐな言葉で紡いでくれた彼女の名前は、友田智佳恵さん。私と友田さんは、普段同じ団体で活動する間柄であり、インタビュー中もいつも通り、フランクに思いを語ってくれた。
友田さんが12歳のとき、母親がくも膜下出血を発症し、障害を負った。それにより、彼女はヤングケアラーとなった。それから現在に至るまで母親のケアを継続しつつ、2人の子どもの子育てや祖母の介護も同時に経験した。現在は、様々な講演会にスピーカーとして登壇し、自分の経験や思いを多くの人に伝えている。
“要は役割を生きている状態だよね。自分自身を生きるというよりは。”
常に家族のケアとともにあった彼女の人生。ケア役割を生きた彼女が見出す、新たな人生の“Role”とは。
【取材・執筆: 氏原拳汰】

ケアの始まりは、友田さんが小学6年生のときにまで遡る。ある秋の日、突如として母親の生命に危機が訪れた。
“その日はたまたま日曜日だったんだけど、お母さんが「頭痛い…」って言いながら、私の目の前で頭を抱えていたのね。でも私はその時、ちょうど反抗期だった。だから最初は、「お母さんが頭痛いって言っているけど、 私は知らない…」っていう感じの態度をとってたんだよ。でも、あまりにもその状態が長く続いたから、これはおかしいと思って…。それで、お父さんを下の階まで呼びに行ったの。
多分「くも膜下出血」って聞くと、いきなり意識を失う様子を想像すると思うんだけど、 お母さんの場合はその時に話もできたし、自分で歩くこともできたから、まさかそんな重大な病気だとは誰も思っていなかった。だから、救急車は呼ばないで、お父さんがお母さんを車に乗せて、近くの緊急外来に連れて行くことにしたのね。”
緊急外来で検査をしたところ、脳出血を疑われた。しかしその病院には、脳神経外科がなかったため精密な検査ができず、母親は救急車で別の病院に運ばれることになった。そして、搬送先の病院で下された診断名は「くも膜下出血」。処置が遅れれば生命に関わる重篤な脳の病気であるため、すぐに緊急手術を行うことになった。
“その時、お父さんから「お母さんが危ないかもしれない」って連絡があったんだよね。それで、私も脳神経外科に足を運んで、手術室に入る前のお母さんと対面したんだけど、その時にはもう意識もなかったし、管に繋がれてる状態だった。
お医者さんからはもう、お母さんの身体が手術に耐えられない可能性もあるっていうことも言われたし、手術が成功したとしても、意識が戻るか分からないことも伝えられた。「もしかしたら植物状態になるかもしれません」って。あと、仮に意識が戻ったとしても、高い確率で何かしらの障害が残ることもあらかじめ伝えられてた。私も、「もしかしたら…」っていうことはすでに覚悟していたんだけどね。”
――当時、まだ小学6年生だった友田さんにとって、あまりにも急展開でしたよね。そのときの心境については、何か覚えていますか。
“まずそもそも、全然実感が湧かなかったのね。お父さんから電話が来た時も、「なんかよく分からないけど、とりあえず呼ばれたから行こう」みたいな。さすがに小6だから、まずい病気なんだろうなっていうのは頭では分かっていたけど。でも、病院に行ってお母さんと対面しても、ストレッチャーに乗っていて意識もないし。それを見ても、やっぱりまだ何が起きているのかよく分からなくて。
それで、やっと実感が湧き始めたのは、手術が始まってしばらく経ってからかな。8時間以上も手術してたからさ、「手術中」っていう赤いランプがずっと灯っていたんだよね。私、廊下のベンチに座りながら、ずっとそれを見ていたんだよ。それを見ていた時に、だんだんと「あれ?」って。「お母さん、本当にこれからどうなっちゃうんだろう」とか、「もしお母さんが死んだら、 私たち家族はどうなっちゃうんだろう」とか、そういう考えがふつふつと湧いてきたの。”
約8時間以上にもわたる大手術だった。幸いにも、母親の身体は何とか手術に耐え、その後、意識を取り戻すことができた。しかし、事前に医師から伝えられていた通り、母親には障害が残り、周囲のケアを必要とする状態となった。
“最初、お母さんは集中治療室に入院していたんだけど、しばらく経ってから一般の病棟に移ることになったの。それで、病院へ気軽にお見舞いに行けるようになって。そこがケアの始まりかなとは思う。洗濯物を回収しに行ったり、家から必要なものを届けたりとかしていたし。でも、お母さんが元気になってほしいっていう思いだけでやってた。今振り返ると、色んなことを担っていたんだけどね。”
母親は脳神経外科からリハビリ専門の病院に転院することになり、歩行をはじめとした身体機能のリハビリを積んだ。その中で体調も少しずつ回復していき、友田さんが中学1年生のとき、母親はついに退院した。
“中1になって、お母さんが家に帰ってきて、ここからが本当の「始まり!」みたいな感じ(笑)。”
――中学生となると、色々と多感な時期ですよね。当時、在宅でのケアを行っていく上で、どのような難しさを感じていましたか。
“入院している時には分からなかったお母さんの障害のことが、暮らしをともにすることで見えてきた部分が大きかった。入院している間は、病院側が担ってくれているケアも結構あったのよ。あと、例えば病院の面会って、30分とか40分とか…、長くても数時間でしょ? だから、短時間しか一緒にいないし、その間はお母さんの意識もはっきりしていた。
でも暮らしをともにして、ずっと連続してお母さん見ていると、「あ、これもできなくなったのか…」って気づくことも多くてさ。スーパーへの道順も分からないし、複雑なレシピが覚えられないのはもちろん、そもそも「火が危ない」とか、「これ以上焼き続けたら焦げちゃう」とか、そういうことすら分からなくなってて。その当時は「もう子どもと一緒だな」って感じてた。”
――中学生ながらに、お母さんを子どもみたいだなって?
“幼稚園児と変わらないなって。とにかくお母さん一人だと、自分の生活を組み立てていくことができないからさ。常にこっちから、「じゃあトイレ行くよ」とか、「ご飯だよ」とか、生活を送る上での全てのきっかけを作らなきゃいけなくって、それがやっぱりつらかったよね。常にお母さんのスケジュール優先で動いていくのがさ。
母親から「朝起きなさい」とか、「お弁当準備して持ってきなさい」とか、中学生だと、まだそういうことを言われてもおかしくない年齢なはずでさ。でも、そういう声かけをむしろ、私からお母さんにしなきゃいけないことがつらかった。”
自分のことよりも母親の生活を優先してきた学生時代。様々な葛藤も抱えた。しかし、母親のケアについて、友田さんが誰かに相談することはなかったという。
“ケアのことを相談したことはほとんどなかったね。なかなか相談しにくかったっていうか…。当時、一緒に住んでいたおばあちゃんが、お母さんの障害を隠したがっていたの。そういう現実があることを子どもながらに感じていたから、中学時代は誰かに相談するっていう選択肢があんまり自分の中になかった。
でも、高校時代になってからは、やっぱり色んなことが見えてくるじゃん。「なんか、自分の家庭って、友達の家庭とは違うな…」とか。 それで、世の中のことも何となく分かってきて、誰かにケアのことを打ち明けたいとは思い始めたんだけど…。でも、誰にどうやって打ち明けたら良いのかが分からなかった。
一番身近な、お父さんにはなかなか言えなかったんだよ。お父さんもケアと仕事を頑張っているのはわかっていたから。それで親以外の大人っていうと、学校の先生はいたんだけど、先生にケアや介護のことを相談するっていうのが、なんかピンと来なくて。だって、別にいじめられているわけでもなければ、子ども特有の悩み相談っていうわけでもない。だから、ヤングケアラー時代はケアのことを相談できなかったよね。ひたすら自分で考えて、自分でやっていくみたいな。”
――相談できないことに、「つらさ」ってありましたか?
“孤独感はあったけど…。振り返ってみると、話を聞いてくれる人がいたら良かったなとは思う。でも多分、「相談しても分かってもらえなかったんじゃないかな?」っていう思いはあるかも。”
誰を頼って良いかが分からない状況の中、友田さんは母親の介護を担い続けた。しかし当時、彼女はそのような状況を当たり前のことだと認識していたという。
“ケアが始まった当時は、それこそ、「ケア」っていう概念を知らなかったんだ。家族だから、当たり前にやるものって感じてた。だから、自分がお母さんに対してやっていることを、「ケア役割」だとは思っていなかったかな。”
現在においても、友田さんの学生時代のように、自分自身を「ヤングケアラー」だと認識していない子どもや若者が多く存在していることが指摘されている。10代前半からケアを行っていた友田さんも、自分がケアラーだと明確に認識したのは、それから10年以上経過してからのことだった。
“20代後半ぐらいのときだと思うんだ。偶然そのとき、難病のお母様を介護する男子大学生の方を特集したショートドキュメンタリーをfacebookで見たのね。それを見て、「私ってヤングケアラーだったんだ」って気づいたの。
言葉自体に対する抵抗感とかも無く、「私がやってきたことは、介護じゃなくって、『ケア』っていう言葉で表せるんだ」って感じて、すごく“ストン”と腑に落ちたんだ。なんか、私の経験が言葉になるんだって思った。
ただ、「ヤングケアラー」という言葉に出会ったとき、まだケアは続いていたけど、私はもう大人になっていた。だからふと、「今の私って何だろう」っていう疑問が生じてね。それで、改めてよく調べてみたら、今度は「ダブルケアラー」や「若者ケアラー」っていう言葉に出会ったの。そのとき、まだまだ私もケアラーなんだって思った。”
――そのときの「ヤングケアラー」という言葉との出会いが、今の友田さんの活動につながったと思うと、言葉の力って大きいですよね。
“やっぱり、「ヤングケアラー」っていうワードで、自分からいろんな情報を取りに行けるようになったのがとても大きかったかな。それこそ、facebookで日本ケアラー連盟*¹とも繋がって、それをきっかけに、スピーカーズバンク*¹の情報を知ったんだよね。
そのときの私は、「自分と同じようなケアラーと出会いたい」っていう思いの方が強かったから、「自分の経験を語ろう」みたいなことは全然考えてなかったんだよ。でも、当時はそこくらいしかケアラーのことを発信している団体がなくて。だから、ここしかないって思って、スピーカー育成講座*¹に参加したの。「いや私、そんなに経験を語る気はないんだけど…」って思いながら(笑)。”
*¹ 日本ケアラー連盟ヤングケアラープロジェクトが主催する「スピーカー育成講座」。家族をケアしてきた10代から30代のケアラー及び元ケアラーを募集し、講演等で自らのケア経験や思いを語るスピーカーを養成することを目的とした企画である。この講座を受講した中で、希望者は「スピーカズバンク」に登録し、その後スピーカーとしての講演依頼を受けることができる。2018年に初めて開催され、2023年8月に第6回目の開催を迎えた。
ちょうどその時期はコロナ禍と重なっており、講座もオンラインで開催された。そのため、当初目的としていたような他のケアラーとの繋がりは残念ながらあまり得られなかったという。しかし、講座からしばらく経ったある日、スピーカーとして初の依頼が彼女のもとに届いた。――
(♯2 「“生き様”を言葉に」 へ続く)
プロフィール
友田智佳恵
12歳のときに母がくも膜下出血で倒れ障害を負ったことにより、ヤングケアラーとなる。当時はヤングケアラーの自覚はなく、大好きな母のためにと、自分にこなせるケアを担いながら学生時代を過ごす。現在は子育てと介護を担うダブルケアラー・元ヤングケアラーとして、様々な講演会にて自身の経験や思いを語りながら、一般社団法人ケアラーワークスのピアサポートスタッフとして、ケアラー支援に携わっている。(Instagram)
インタビュアー・執筆
氏原拳汰
元若者ケアラー。大学時代にレビー小体型認知症の祖父の介護を経験したことから、ヤングケアラー・若者ケアラーへの支援の取り組みに関心を持つ。現在は心理系の大学院に通いながら、ヤングケアラー協会の活動に参画中。また、友田さんと同じく、一般社団法人ケアラーワークスでもアルバイトスタッフを務める。(個人HP)
執筆協力
そら
元ヤングケアラー・現若者ケアラー。重度の障がいのある弟のケアをしている。将来はケアラー支援に携わる仕事をしたいと考えており、社会福祉士の取得を目指す。ヤングケアラー協会が主催するイベントにも参加している。