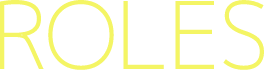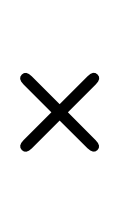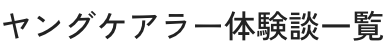“しんどさ”にケーススタディは成り立たない。ヤングケアラーとして三島俊祐さんが今日も発信し続ける理由。
2025.04.05
大学2年生の時から4年間、母親のケアを担った三島俊祐さん。「母のケアはやりたくてやっていた」一方で、精神的に落ち込む家族を支えながら誰にも相談できない日々を過ごした。そんな三島さんが「ヤングケアラー」という言葉に出会って救われたこと、現在の活動のきっかけになった想いについて。
――まず、三島さんのケアの経験について教えてください。
ケアが始まったのは大学2年生、20歳のころです。母親が乳がんのステージ4の状態で見つかって、そこから4年くらいケアをすることになりました。当時は、大学で作業療法士を学んでいたので、母のリハビリのサポートはじめ洗濯や掃除といった家事などは、基本的に僕がやるようになりました。
でも、実は当時やっていたのは母親のケアだけじゃないんです。同じ時期に、姉が職場でいじめに遭ってうつ状態になってしまって、父親も、母のことで精神的に不安定な状態でした。
家族間のコミュニケーションが取れないので、僕が姉の様子を見に行って、その話を父親に「今日こんな感じだったよ」と伝える。ケアの合間に僕がそれぞれの話を聞くという感じで、お互いの橋渡し役のようなことをずっとしていたんです。
――家族全員のケアを担っていたということですね。
母親の病気が見つかってから、バタバタとやることが増えていった感じでしたね。母のケアについては、もちろん大変なこともありましたけど、どちらかというとやりたくてやっていたんです。姉と父親の橋渡し役になることの方がしんどかったですね。
自分がしんどいことは誰にも言えませんでしたし、本当は家族みんなで母のケアをやっていきたいのに、自分だけが抱えてしまうという環境がずっとあったと思います。母のがんは手術で切除していったんは寛解したのですが、4年後に再発、余命宣告を受けて1ヶ月後には亡くなりました。
――当時、どんな支援があればよかったと感じますか?
正直に言うと、何か行政的な支援がほしかったわけではないですね。一番しんどかったのは「自分がしんどい」っていうのを吐き出せる場所がなかったことです。周りに話を聞いてくれる人がいたら、少し違ったのかなという気はします。
ただ、母が亡くなってからのケアは欲しかったですね。母が亡くなってから、介護ロスみたいになってしまって。
僕の実家は小規模のデイサービスをやっていて、母親は介護の仕事をずっとしてきた人なんです。作業療法が学べる大学のことやリハビリの仕事を知ったのも、「こういうのがあるよ」って母親が教えてくれたからで、母親とはずっと一緒に夢を追いかけてる感じがあったんですよね。
だから、燃え尽きというか、生きがいがなくなった感じになってしまって、大学も4年生で中退してしまったんです。
―― 周りから「それはもったいない」って言われませんでしたか。
めちゃくちゃ言われました、あと1年なんだからって。でも、もう誰から言われても何も響かないというか。
自分にとって大事な人を失ったっていう喪失感が大きすぎ、そこでプツンと切れてしまって、中学、高校、大学と、友人関係もほとんど絶ってしまいました。
周りを見るとどうしても、キャリアを積んでいる友達もいれば、結婚したっていう人もいる。誰かと比較して劣等感を感じたり、友達に会わせる顔がないように感じたりして、結局自分から一人になってしまったところがありました。
――三島さんが、ヤングケアラーという言葉に出会った時はどう感じましたか?
僕がヤングケアラーという言葉を知ったのは、社会人になって3年目です。たまたまテレビでヤングケアラーの特集を見て。それで「あ、自分にもそういう時期があったな」と思い出して、「ふうせんの会」に参加させてもらったりするようになりました。
同じような経験を持つ人たちと集うことですごく救われましたし、分かってくれる仲間が増えたというのは間違いありません。自分のことを真摯に受け止めてくれる仲間に出会えたのは、すごく大きかったと思っています。
――ヤングケアラーに関する発信活動もかなり積極的にされていますが、そういった想いとも関係があるのでしょうか。
ヤングケアラーという言葉が、もっと「正しく」認知されてほしいっていう想いがあるんですよね。
ヤングケアラーと言っても、一人ひとり、ケースが全然違います。ケーススタディが成り立たないというか、同じような人がいないっていう難しさがあります。
というのも、以前、僕のことを「ケアの期間が短かったから乗り越えられたんだね」みたいに言われたことがあるんです。確かにケアの期間が長引けばそれだけ大変ですが、ケアって期間の長短ではないですよね。
僕自身が経験してきたことも正直しんどかったですし、長い短いとか、何歳からとか、ましてや、その大変さを他人が測れるものでもない。みんなそれぞれしんどさを抱えているということを、まずは知ってもらいたいっていう気持ちがあります。
もちろん最初は自分の経験を話す怖さもありましたが、そこは自分が切り出していかないといけないという気持ちがあります。自分の経験を知ってもらうことで、いろんな人がいるんだよ、ということは伝えていきたいです。
――ケアの経験が、今に生きていると実感することはありますか?
この春から、友人が合同会社IKMを立ち上げ、訪問介護スタッフとして働いています。友人からの誘いがあった時、介護業界に戻ることに迷いはなかったですね。
母親の仕事をずっと見ていて、憧れを持っていたというのもあります。母の葬儀の時には、本当にたくさんの人がきてくれて。利用者さんが手押し車を押しながら来られて、最後に手を合わせてくださるのをみて、母親ながら人としての偉大さを感じました。
いろんなケースがあって、さまざまな利用者さんに出会いますが、「もっと早くあなたのような介護士に出会いたかった」と言ってくださることもあって。もし自分がこの経験をしていなかったら、きっとそこまで言われなかっただろうなって思います。
母を亡くした当時は自分には何もないように思っていましたが、この経験があるからこそ社会に必要とされていることも実感しますし、僕にとっては天職だと思っています。
――手作りの折り鶴ストラップを配布する活動もされています。きっかけは?
よく聞いていただきました(笑)。 これはもう僕のライフワークになっていて。折り鶴のストラップを作って出会った人に配っているんですが、もうすぐ1000個になります。
きっかけは、母親の遺品整理をしていた時たまたま折り紙を見つけたこと。当時、引きこもりのような状態で何もできなかった時期だったので、「これで何かできないかな」と思ったのが最初です。それで「これを配り切るまで帰らない」って決めて、石川県の方へ一人旅に出ました。
僕は、自分の経験からも、人と出会うことって本当に大事だなって思っているんです。人との出会いを大切にしたいっていうのもありますし、僕自身、”ちょっと変わった人でありたい”っていう想いもあって。人と違うことをやることで、誰かの記憶に残るかもしれない。そこから、つながりが生まれるんじゃないかと思うんですよね。
折り鶴は、1000個を配り終えたら、次は1万個を目指すつもりです。
――三島さんらしい活動ですね。振り返ってみて、当時の自分に出会ったとしたら、どんな言葉をかけたいですか。
そうですね……やっぱり「何かあったらいつでも言ってね」になるかな。
SOSを出すタイミングは、人それぞれだと思うんです。いきなり声をかけられても、本当にしんどい時は無反応かもしれないし、どう反応すればいいかもわからない。
今じゃなくてもいいから、話してみようかなっていうタイミングが来たら、いつでも話してくれたらいいよ、っていうスタンスで声かけをするかなと思います。
人と出会うことを途切れさせないでほしいって思いますね。今ある出会いも、これからの出会いも大切にして、僕自身も、「しんどい」と伝えてくれたその時にすぐに動けるようにしておきたい。つながり続けることで、誰かの力になれるような活動を続けていきたいです。
三島 俊祐(みしま・しゅんすけ)
1994年、兵庫県生まれ。大学生の頃にガンになった母親のケア、家族の精神的なサポートを4年間行う。介護事業を行う合同会社IKMで働きながら、人とのご縁を繋ぐ「折り鶴ストラップ」を作り全国各地でつながりを作っている。