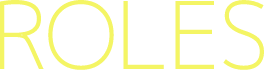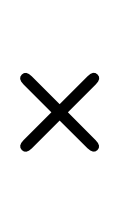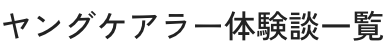「弟が幸せに過ごすための施設を、地元につくりたい」。
幼馴染と学生起業した宮川快さんを後押しする、家族と地元に対する想いとは。
2025.03.26
取材中、一貫して「弟と母が幸せでいて欲しい」と繰り返した宮川さん。2歳年下の弟のケアをシングルマザーの母と共に担ってきた。地元の香川を離れ、東京の大学で学びながら幼馴染と起業した理由も、弟に対する愛情が起点となっている。宮川さんを突き動かす、家族と地元に対する想いを聞いた。

ーはじめに、自己紹介をお願いします。
香川県で生まれ、大学入学のタイミングで東京で一人暮らしを始めました。今、4年生で休学中です(2025年3月現在)。3年生の時、幼馴染と共に、福祉や介護に関する事業で起業をしました。
ーご家族についてお伺いできますか。
母と、生まれつき障害を持つ2歳年下の弟と僕の3人。母と弟は今も香川で暮らしていて、僕が上京した時から祖母がサポートをしてくれています。
弟は、脊髄小脳変性症といって、脳が時間が経つにつれてだんだん小さくなっていく病気で、知的障害と身体的障害がある状態です。
ヤングケアラーという言葉にはここ数年で出会ったのですが、つい最近、ヤングケアラーに関するイベントにボランティアとして参加した時に、自分自身もヤングケアラーだったのかもしれないと気付いたばかりです。それまで意識したことはなかったです。
ー弟さんのケアは、どのようなことをされていたのでしょうか。
弟の病気は徐々に進行する感じだったので、がっつりとケアを始めたのは自分が10歳くらいの時からと記憶しています。日常生活で必要不可欠なこと全般の介助をしていました。例えば食事をつくるのもそうですし、食べさせてあげることや、入浴、トイレ、歩行介助。外出する時には車椅子の操作も手伝いますし。 母は仕事で朝出勤し、帰るのは18時頃。弟は平日、デイサービスを利用していましたが、母が家にいない時には僕が見守りをしないといけないので、負担でいうとそれが一番大きかったかなと思います。
ただ、僕は友達と遊びたいという気持ちが強くあったので、友達を家に招くことが多かったですね。弟に気を配りながら片手間で遊ぶという形で。僕、出身が田舎なので、保育所から中学校までメンバーがほとんど変わっていなくて。
だんだん自分のことを理解してくれる人が増えていく周辺環境だったのは、すごく大きかったです。家から近いところに友達がいたので、幸いにも助けて欲しい時に「助けて」って言えたんです。
行政サービスなどを利用し始めたのは5年くらい前です。よくしていただいていた訪問リハビリの先生から「いろんなサービスがあるから社会福祉士の人に相談してみたら?」とアドバイスをいただいたことがきっかけです。
母はそれまで、どこに相談すればいいのかが分からなかったと言っていました。相談後、いろんなサービスを利用することができました。初めて社会福祉士の人と話をした時に言われた「お母さん頑張りすぎです」という言葉が印象に残っています。振り返ってみれば、必要な情報を手に入れるのが難しかったのかなと思います。

ーご自身の進学で東京へ出ていくことに対する迷いはありませんでしたか。
もちろん常に家族に対する心配はあるのですが、東京でしっかり勉強して、香川に持って帰りたいっていう気持ちが強くて。香川に残ることも考えましたが、東京でたくさんの人に出会い、競争力の高い中に飛び込んでさまざまな経験を積むことが自身の成長につながると考えていました。通っていた高校がいわゆる進学校だったのもあり、盲目的に「いい大学に入って、 4年後にいい就職先を見つけて働く!」という敷かれたレールの上を歩いていたのが、僕の高校時代。 同時に、弟に貢献する仕事に就きたいとずっと思っていました。
進学の資金面は結構心配でした。父と母は僕が幼い頃に離婚していて、その数年後に父は亡くなっていることもあり、学費は母が、生活費は自分で頑張って稼いでいます。母も大変だったと思います。
ー学生起業をされたとのことですが、福祉と介護をテーマに取り組んでいるのは、ご自身のケアの経験があってのことなのでしょうか。
そうですね。弟自身が「入りたい」と思えるような施設を地元の香川でつくりたいというのが目標としてあります。以前、弟が利用していた施設に見学に行った時に、見たくもないテレビを見させられていて、ずっと「ぼーっとしていて、めちゃくちゃ退屈そうに過ごす弟の姿を目の当たりにしたことがきっかけの一つです。これはいかん…と思って。
大学入学当初、話題になっていたAIの開発に関心があって、理工学部の情報工学科を選び、ロボットをつくるとか、プログラミングの勉強をずっとしてきました。それもあって、AIを使って福祉的なサポートや医療的なサポートができたらいいなぁと考えていました。ただ、自分が好きな「AIを使う」という手段は、弟に貢献したいという自分の想いに対して、遠回りしてアプローチしている気がしてきたんですよね。もっと直接的にアプローチできるやろって思い直したのが、大学2年生の時なんですよね。

ー「弟が入りたいと思えるような施設をつくる」という目標に変わったんですね。
その方が、自分が見たい景色が見れるなって思ったんですよ。弟にどう貢献するかっていうことを改めて考えた時に、弟に豊かに暮らして欲しいなっていう気持ちが強くあって。
僕は、介護は生活を支えるセーフティーネットというか、インフラのようなものだと考えています。つまりなくてはならないものです。ただ、それだけあっても豊かな暮らしは実現しない。豊かな暮らしには介護+αが必要ではないかと。この+αは、それぞれの「ワクワクするもの」「やりたいこと」の実現が大事だと思っています。施設に入ると、身体的にも施設のルール的にもさまざまな制限が生まれ、自宅とはかけ離れた暮らしになりがちです。その制限の中でも、楽しさ、豊かさを最大化し自宅の暮らしに近づけていきたい。それが具体的に何なのか、どうアプローチしたらいいのかは、今探求しているところなんですけれど。
僕がCOOをしているHelow株式会社では、物理的な介護はやっていなくて、「遊ぶことと働くことの探求を、介護に組み込むことで豊かな暮らしが実現していくのでは」という仮説を持って、「NewNeighbor」という介護保険外の自費サービスを提供しています。「ヘルパーさんからおとなりさんへ」というコンセプトのもと、利用者の趣味ややりたいことに焦点を当ててサービスを提供しています。基本的には、日常生活で困ったことがあればお手伝いします。一方で、若い子とランチを希望する方とランチのセッティングをしたり、利用者から仏語を教えてもらいながら仏語で映画を見たりすることもあります。このように持ちつ持たれつの関係性を意識して、利用者の生きがいづくりに伴走しています。
ー幼馴染と立ち上げたそうですが。
はい、1歳の頃から付き合いのある河田 創志郎に誘われる形で始めました。共同創業者である河田自身は、上京前から起業することと僕のことを誘うことだけは決まっていたみたいです。ただ、どんなテーマ、分野で事業を起こすのか定まっていなかった時に、「そういえば」という感じで、僕の弟に対する悩みを気にかけてくれました。僕が小さい時から弟に貢献したいと言っていたので、せっかくならそれを解決できるような事業をやってみないか、と言われたのが始まりです。河田は幼い頃から僕の弟と関わる機会がありました。その分、僕のことも弟のこともよく分かってくれている存在でした。

ーこれからの展望をお聞かせください
弟が入りたいと思えるような施設をつくりたいというのに加え、もう一つは、母や祖母が入りたいと思う、老人ホームだったり…形は何でもいいんですけど、暮らしの豊かさが担保された施設を香川につくりたい。 福祉施設で起こった不穏なニュースなどを見ていると、家族を預けざるを得ない状況だとしても預けたくないって思ってしまうことがあって…。それって、悲しいじゃないですか。世の中にある既存の施設を変えていくのは難しいかもしれないけれど、自分が欲しいと思うものを自分でつくってみたいです。
もしケアの経験がなかったら、普通に大企業への就職を目指してプログラミングなんかを頑張っているんじゃないかな。僕は、家族が大好きで。 家族に対する愛情みたいなのが、僕のエネルギーになってるんじゃないかと思っています。 愛情がなかったら、多分起業の一歩が踏み出せてない気がしています。今提供しているサービス「NewNeighbor」についても、利用者が自分の家族だったら?と想像して取り組んでいます。
最初は事業にするつもりもなく、根っこは弟と母に幸せになって欲しいという気持ちがあって、徐々に周りを巻き込みながら形にしてみたいなと思うようになりました。僕は起業の形を取りましたが、家族のケアを経験してきた誰もが無理に一歩踏み出さなくとも、目の前にいる家族を幸せにしてあげる…それだけで充分だとも思っています。一歩踏み出したい場合は、友人だったり、サービスなどを頼ってみるといいんじゃないかなと思います。
宮川 快(みやがわ・かい)
小学生の頃から、障害を持つ弟の介護を経験したヤングケアラー。現在は大学を休学し、介護事業で起業。介護生活に豊かさを見出すために、自費サービスを提供している。将来は、地元香川県で家族のための施設を作ることが夢。 ( 宮川さんのFacebook ・ 会社のInstagram )