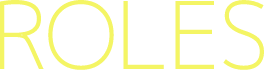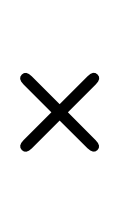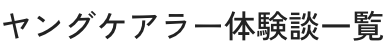「子どもや若者が自分の意思で人生を選択できる社会へ」
子どもたちの「やりたい」を叶える原田伊織さんの挑戦
2025.03.12
「ヤングケアラーが抱える最大の課題は、やりたいことに挑戦できなくなることなんです」そう強く語るのは、自身も高校の3年間、家族をケアした経験を持つ原田伊織さん(22)。ケアが人生のすべてにならないよう、子どもや若者が自分の想いを大切にしながら、それらを社会で実現するための道を拓こうと多角的な視点を持ちつつ、日々奮闘を続ける。
――まずは自己紹介と、現在、原田さんが携わっている活動についてお聞かせください。
大阪人間科学大学4回生で、学業のかたわら、兵庫県尼崎市を拠点とした地域活動を行っています。
具体的には、スケードボードのイメージ向上や、練習環境を整備しようと活動するNPO法人ASKの理事、また地域の課題解決のため行動する、全国の若者同士のネットワーク構築を目的とした全国ユースカウンシル連盟の共同発起人なども務めています。
令和5年度からはこども家庭庁こども家庭審議会の委員にも選定され、より広い視点を持ちながら、「これがしたい」「こうありたい」と願う子どもや若者たちの“リアルな声”を拾い上げるよう、挑戦を続けています。
いずれの活動も、子どもや若者が、自分の意思で人生を選択できる社会づくりに貢献したいとの思いから携わっています。

――精力的に行動されていますね。活動を始めるきっかけは何だったのでしょうか。
僕が通った高校は介護福祉士の資格の取れる福祉系の学校で。授業を受けるなかで、本来ならリラックスできるはずの家で、誰にも相談できずに介護やケアを担う同い年の子たちがいることを初めて知ったんですよね。
「何とかしないと」と強く感じ、当時、高校のあった尼崎で実施されていた、若者が地域の中でテーマを設定し活動するプログラムへ参加を決めました。自身のメインテーマを「ヤングケアラー」と決め、高校3年生の冬から活動をスタートしたんです。
活動を進めるなかで当事者の話を聞く機会が多く、ある時、彼らの境遇が自分にも当てはまっていることに気づきました。そのときからようやく「もしかすると、僕はヤングケアラーなのかもしれない」と思い始めましたね。
実は母は、僕が高校1年生のときにうつ病を発症していました。僕が幼い頃に両親が離婚していたため、僕を含む兄弟4人は母が一人で育ててくれたんです。仕事もしてはいたものの生活保護を受けながらの生活で、きっと身体的にも精神的にも負担はかかっていたんでしょうね。後になって、会社から家までの道を泣きながら帰ることもあったと母から聞きました。
病気になった頃はとくに家庭の問題が重なった頃で、あるとき「うつ病だと診断された。」と母から打ち明けられました。

それまで、僕たち子どもの前で涙を見せなかった母が感情を乱すことも増え、夜の10時から明け方4時頃まで母の愚痴を聞くこともたくさんありました。話の内容はたいてい仕事か家族のこと。夕飯も食べず、何度も同じ話を繰り返し聞かされることもあって。
寝不足の日が続き授業に支障が出ることもありましたし、客観的にみたら「しんどい」状況だったと思います。ただ以前から僕と母は会話の多い親子関係だったためか、その状態をとくに「ケアしている」とはとらえていませんでした。
――ヤングケアラーであることを自覚しない子どもたちは多いと聞きます。
線引きは難しいですよね。進学先の大学の教授にヤングケアラー問題を専門にされている方がいて、僕はその先生に実情を聞いてもらい、少しずつヤングケアラーの自己認識を持ちました。
ヤングケアラー当事者の会である「ふうせんの会」にもつながり、いろいろな人にこれまでの自分の経験を聞いてもらうなかで、ようやく「僕もヤングケアラーだと名乗っていいんだ」と思えるようになったんです。そこからより積極的に、ヤングケアラーの支援活動などに携わり始めました。
――今はご家族とどのように関わっているのでしょうか。
大学進学と同時に実家を離れ、今はシェアハウスで暮らしています。母の症状は落ち着いていて、定期的な通院も必要ないと言われています。実家には月に一度、帰るかどうか、くらいですね。
とはいえ、以前は「家を離れることはできない」と思っていたんです。一泊程度ならまだしも、病気の母を放って何日も家を空けるのはとても不安でした。
ただ、活動を通して出会った信頼する地域の大人が「一回家を出てみなよ」と声をかけてくれたんですよね。まずは1週間から、と背中を押してくれて、実際にやってみると、心配していたような事態にはならなかったんです。
最初は母の様子を想像してはずっとそわそわしていましたが、少しずつ慣れてきて。僕自身も気持ちがとても楽になり、母は母でお気に入りの音楽を楽しんでいて「あぁ離れていても、お互い自立して生きていけるんだ」と体感し、今の暮らしを選択できたと思います。

ケアをしていたからこそ、とむやみに美談にはできませんが、それでも母の話をじっくりと聞くなかで、人の話を聞く胆力も鍛えられた、と感じています。これは今、介護のバイトをするなかでも使えるスキルになっていますね。
――原田さんはご自身の経験を通して、ヤングケアラーが抱える課題をどのように整理し、今後、どのような支援が必要だと考えていますか。
ヤングケアラーであることの最大の問題点は、家族のケアが理由で、子どもが本来やりたいと思っていることにトライできないことだと考えています。
ヤングケアラーの置かれた環境をマイナスと捉え、改善のためのヘルパー派遣を実施するなど、各自治体でさまざまな動きが見られるようになりました。ただ僕自身は、そういった被害救済的なことだけではなく、子どもがやりたいことに挑戦できる仕組みや社会づくりに目を向けたいと思っています。
今、僕がNPO活動を通してスケートボードパーク建設のために動いたり、ユースカウンシル連盟を作って若者の声を集めようとしたりするのも、すべて子どもや若者が、やりたいことに向けチャレンジするのを応援したいから、なんですよね。
――直接的なケアではなく、アプローチの方法を変えたということですね。
「ヤングケアラーがケアと自分の人生のバランスを選択できる社会にする」という想いを大学の4年間、ずっと大切にしていました。尼崎でもさまざまな活動にチャレンジしましたが、やはり学生であることの限界があるんですよね。
子どもたちとつながっても、結局、具体的な「ケア」の領域になると、僕たちでは手に負えない部分もありました。それなら、子どもたちが自分の人生をしっかりと歩めるように、自分のやりたいことを叶えられる社会づくりを目指していこうと視点を変えたんです。
――原田さんのなかで、すべてはつながっているのだと感じます。今後の活動目標もぜひ教えてください。
まずはすでに着手しているスケートボードパーク建設を成功させます。「スケートボードを練習する場がない、作りたい!」という若者の想いがきちんと形になって、声をあげれば必要なところにちゃんと届くんだよというメッセージを全国に届けていきたいと思っています。
そうして、全国でまた若者たちの生活を変える新たなきっかけが芽生えたら嬉しいですし、新しいつながりが何らかの形でまた、尼崎に戻ってきたら最高ですよね。
もうひとつの目標は仲間を増やすこと。NPO法人も連盟の活動も、コアメンバーはいるものの、その周辺がなかなか増えなくて。人を巻き込みながら活動を続け、子どもや若者がもっと幸せに生きられるようにしたいです。

――家族のケアを経験した原田さんが、今まさにヤングケアラーとして日々を生きる子どもたちに伝えたい想いは何でしょうか。
自分の好きなことに没頭できる自分のための時間を、1日のうち、たとえ少しでもいいので持ってほしいと思っています。起業しよう!といった大きなことでなくて、将棋でもゲームでも、ささいなことでもいいです。
「とてもそんな状況じゃない」という場合もあると思うのですが、自分の生活がすべて家族の介護だけになってしまうと、そのケアが終わったとき、「自分の人生は何だったんだろう」と喪失感に襲われることがあるんです。
僕自身も、母の状態が落ち着いた頃、身体は楽になったはずなのに、いつも母の話を聞いていた夜の時間がぽっかりとあき、気持ちが落ち着かなくなったことがあって。誰かのための人生ではなく、自分の人生をしっかり歩んでほしいですね。
もうひとつは、自分の”応援団”を見つけてほしいということ。病気の家族には専門職による支援もつきやすいのですが、支える子どもへのサポートは抜けがちです。
僕は正直、ヤングケアラーである状況は、変えようがないとも感じています。ある意味、しょうがないっていうか。ヤングケアラーという言葉は広まりつつありますが、だからといって誰かがたいへんな現実をすべて変えてくれるわけでもない。だからこそ、そんな自分を応援してくれる応援団をいろいろな場所で持ってほしい。
僕も、学校の先生が話を聞いてくれたり、バイト先が家のことを気にせず過ごせる場所であったり、何より、地域活動の拠点であった尼崎のユースセンターが心のよりどころになってくれていました。
自分の世界が家族だけにならないためにも、支えとなる存在を見つけてくれたらと願っています。
原田伊織(はらだ・いおり)
2003年兵庫県生まれ。2歳で母子家庭になり、5人家族で生活保護を受けながら育つ。高校1年生の時に母親がうつ病と診断を受け、家庭内で精神的なサポートをしてきた。 2021年7月のつどいへの参加をきっかけに、元ヤングケアラーのピアサポーターとしてふうせんの会に参画。大学で社会福祉を学びながら、ふうせんの会や尼崎市でのヤングケアラー支援に取り組む。 2023年4月よりこども家庭庁こども家庭審議会の委員に就任。