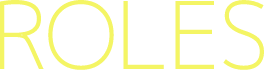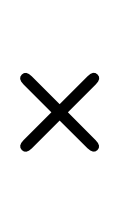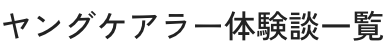あなたを助けたいと思っている人は、きっといる。何気ない会話から孤独を防ぐ、吉田綾子さんが大切にしたい支援のあり方。
2025.02.26
保育から障害福祉、ヤングケアラーと、子どもから高齢者まで幅広い支援にあたってきた吉田さん。パーキンソン病だった母の32年間のケアを経て、「孤独だった」と語る自身の経験をきめ細やかな支援網に活かしながら、今も当事者たちと向き合い続けている。
ー自己紹介をかねて、現在の活動に至るまでの経緯を教えてください。
母親がパーキンソン病を患い、高校1年生の頃からケアが始まりました。短大を卒業して保育士として働いていたのですが、途中で障害福祉関係の仕事につきました。32年間ケアをして、6年前に母を看取りましたが、その間、仕事をしながらケアにあたっていたという感じです。
仕事は障害福祉が長かったのですが、高齢者介護の技術も身につけたいと思ったので、途中で介護福祉士を取りました。児童から高齢までを経験をさせていただいて、現在は障害福祉サービスの相談支援専門員、介護で言ったらケアマネージャーさんみたいな仕事をもう8年ぐらいさせてもらっています。
ー母さんのご症状はどうだったのでしょうか。
母がパーキンソン病を発症したのは、50歳になるかならないかくらいの頃です。私が17歳くらい、ちょうど平成に入る頃だったと思います。
最初は鉛筆を持ったりとか、手が震えて止まらないっていうところからだったのですが、それが身体的に広がってくるんですよね。そのうち、足腰が弱くなり、足が不自由になってきて、最後はもう会話もできなくなる感じでした。
ただケアで大変だったのは、母は身体機能の低下とともにメンタル的な落ち込みがひどかったことです。精神的な幻聴、妄言もあって、最後の方はメンタルと身体的なケアの両方になっていって、それがだんだんしんどくなっていきましたね。

ーご自身ではケアの状況をどのように捉えていましたか。
母はパーキンソン病になる前から精神的に不安定なところがあって、寝たり起きたりを繰り返していたんです。だから、小さい時から家のお手伝いをするのが当たり前で、お母さんからも家のお手伝いしなさいってずっと言われてきたし、もうそれが普通だと思っていましたね。
父も昭和一桁生まれで、昭和の男尊女卑時代を生きてきた人です。6歳上の兄がいますが、跡取りで男だからということで、兄とはお互いに一人っ子みたいに育てられました。だから、逆に兄がケアに入ると怒られる。私の時代は、そうした昭和の価値観が当たり前でしたが、私よりも下の世代の中でも、その認識が根強くあるのを感じることはありますね。
ー当時、周りの方との関わりの中で、誰かに相談することなどはできましたか。
できなかったですね。父は「家の恥を外に晒らすな」という考えで、こういうことは絶対言っちゃだめだと言われていました。母も、人付き合いを拒むようなところがあって。発症から 10 年以上経ってようやく介護認定を取ったのですが、母は、ヘルパーさんが来る前に私に「家の掃除をしてくれ」と言うんです。そして、ヘルパーさんが来たら、もうヘルパーさんにお願いすることはないから「帰していいよ」と伝えてほしいと言ったり。
ケアマネージャーさんもついていたのですが、そういう家の状況を説明したりもないですし、聞かれることもない。周りの人も、私のことはただ娘であり”母の手伝い”としてしかみていないので、そこに気遣ってくれる人、相談できる人というのは最後の最後までいなかったです。
ー現在は、北海道ケアラーズなどを通して当事者への支援活動をされています。昔と今とで、課題の変化を感じられることなどはありますか。
私は、自分のケアの体験にテーマをつけるとしたら、「孤独」なんです。私の場合は、嘘つかなきゃいけない、ケアしてることはなかったことにしなきゃいけない、というのがすごく辛かった。
もともと母とはソリが合わなくて、母親の一部のように私を扱うようなところがあったので、ほっとした部分もありつつ、母が亡くなってなんだかモヤモヤが残っていていたんです。それでネットで調べたり、自分で少しずつ発信したりするようになって、「ヤングケアラー」という言葉に出会いました。

今は母子家庭のご家族をサポートさせてもらうことが多いのですが、人とは関わりたくないと考える若いお母さんが増えているような気がします。その点では、孤立が孤独が進んでいるなという印象があるんです。
でも人は頼らないと生きていけないですよね。実際に支援に繋いで、結果的に分離が起こったりすることもあります。でもそうなる前に、何かできることがあったはずなのに、拒んでしまうのはなぜなんだろうと思うことはよくあります。
確かに今の時代、子どもが泣いたりすると近所から苦情が入ったりして、子育てそのものがしにくい。私の時代はまだ昭和的な近所付き合いがなんとなくあり、近くのおじいちゃんおばあちゃんが子どもたちを気にかけてくれる雰囲気がありました。私の家族は一切シャットダウンでしたが、今の世の中でもそういうリアルなつながりを活用しようと思えばできなくはない、と思っています。
ーリアルな繋がりを保つことで、気持ちが楽になったり負担が軽くなったりすることもありますよね。子育てもケアも、みんなで取り組んでいく方法を、もっと見直していってもいいのかもしれないと思います。
そう思います。今の若い人たちは、いろんなコミュニティを探してる人が多いですよね。でも、わざわざそういう形を取らなくても、他愛のない話ができる周りの大人がいれば、少しでも違うのかなという気がします。
私は、家のことがどんなにしんどくても毎日学校には普通に通っていたんです。でも門限が5時。なるべく帰るようにはしていたものの、やっぱり家には帰りたくない。それで、放課後によく友達とカフェ行ったりぶらぶらしたりしていました。もちろん、そこで本当のことが言えるわけではないのですが、「こんなことがあってさ」みたいに、軽くお喋りできただけで「あ、吐き出せた」っていう実感がありました。それだけでも十分「がんばろ」と思えたんですよね。
当時、もし周りに「相談受けますよ」っていう人がいたとしても、私なら絶対相談していないです。でも、何気ない働きかけやおしゃべりの中で、ポロッと本音が言えるようなことがあったら、それだけで全く違ったのではないかと思います。
障害福祉の仕事でも、お子さんにケアを担わせてるケースを目にすることがあります。そういう時は、お子さんがいる時間帯に訪問したりして、”気にかけている”という言葉にならないコミュニケーションを繰り返しています。部屋から出てくることがなくても、時間をかけてちょっとずつ会話ができる信頼関係を作っていきたい、という気持ちはありますね。

ー吉田さんご自身が、ケアや仕事を通じて得られた経験というのはどういうものだったのでしょうか。
福祉の仕事では、パーキンソン病の方の介護に入ったこともありますし、そういう意味では母のケアにも役立ったというか、働きながら勉強させてもらいました。
福祉も含めていろんな活動をして気づいたのは、私が想像している以上にいろんな人がいるということです。当時の私は、社会は冷たいなと思っていました。私はケアをするけれど、個人としての私は”いないもの”として扱われましたし、大人はそういうものなんだと思っていました。でも、違うんだなって。
福祉の仕事をしている人って、すごく人を見ているんです。言葉にできないことやタイミングを見ながら、見計らって手を差し伸べたい、と思っている大人はたくさんいます。それに気づいた時、じゃあ私がもしあの時「今、大変なんだよね」って言えていたら、何か変わっていたのかもしれない。「なんかできることないかい?」って言ってくれる大人もいたのかもしれないなって思いますね。
ー今、孤独を感じている当事者である方がいたら、ぜひ吉田さんや支援につながってほしいです。最後に、これからやっていきたいことについて教えてください。
最近、自身の経験談を本にしました。自分自身の経験が誰かの一助になればいいなって。そんな思いで書きました。
あとは北海道の課題で言えば、全体が高齢化していることもあり、「所詮、家族の手伝いだよね」と言われることがやはり多いと感じています。都会と比べると、まだまだヤングケアの認識そのものが10年 、20 年遅いという感じ。ですから、私たちも北海道だけで完結するのではなくいろんな方と繋がって、発信していくことが課題だなと思っています。
私は、福祉でもケアでも一貫して家族というテーマで考えてきました。福祉の道に進んだのは、私のような人を増やしたくないと思ったからです。家族という 1 つの単位にいろんな課題があるので、その課題の何かしらを解決できる1 人でありたいなと。
でも、そこも少しずつ若い世代に明け渡していきたいという気持ちもあります。福祉に携わっている方々も高齢化しつつあります。若い人たちが飛び込んでも、なかなか働きづらい環境になっているところもあります。
当事者の人たちが少しでも心軽くなって自分の道を進んでほしい。そのためにも、自分たちの下の世代に何かしら手を差し伸べられるものを渡して、私自身も少しずつ引いていきたいというのが次のステージで考えていることです。
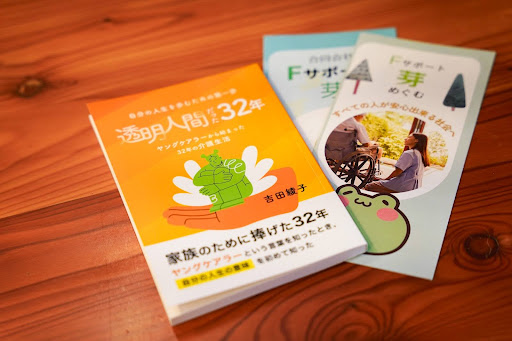
吉田綾子(よしだ・あやこ)
北海道札幌市生まれ。高校1年生の時に母親が難病のパーキンソン病を患い、32年間母親のケアを担ってきた。現在は障害福祉サービス事業の会社を運営し、相談支援専門員として業務に当たりながら、一般社団法人北海道ケアラーズに所属し、ケアラー支援の普及啓発活動も行っている。