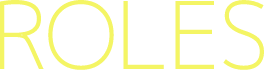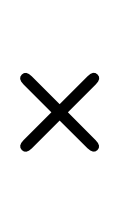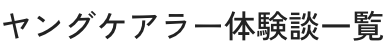「誰かの安心できる一瞬になりたい」。24年間の母のケアを経て、ヤングケアラー支援にかかわり続ける高岡里衣さんの原動力とは。
2025.02.12
9歳から始まった母親のケアを「必要以上にネガティブにもポジティブにも思っていない」と語る高岡さん。自分の経験を振り返り、過去の自分のような人に伝えていきたい、との思いで今も続ける発信活動は、ヤングケアラーという枠組みを超え、子どもたちを取り巻く社会課題を見据えている。
ーまずは自己紹介をお願いします。
私が9歳の頃、母が難病になり、そこから24年間、母のケアをしてきました。 ケアには色々段階がありましたが、最終的に母はほとんど身動きが取れない状態だったので、在宅療養での闘病生活を家族で支えていました。母がこの世を旅立ってからは、ケアロスなども経験しながら今は人生の再構築をしているところです。
ー子ども時代からどのようなケアをされてきたのでしょうか。
子どもの頃は、母は入院していることが多かったので、買い物、掃除、洗濯、食事の準備、お見舞い、感情面のサポート、入院をしていない時は通院の付き添いなどもしていましたね。家族それぞれが自分でできることを自分でしないといけなくて、他の家では親にやってもらえるようなことも当たり前ですが自分でやらなければいけない。私はもともとお母さん子で家の手伝いをよくしていたのですが、そうした流れもあって、ケアは自然と私に偏っていったと思います。
だからといって、当時はそれが特にネガティブなこととも思ってなかったんです。「家のことが忙しい」くらいの感覚で。学校にも行っていたし、友達もいたので、外から見たら普通の学生だったと思います。
ただ、私が大学を出て社会人2年目の頃、母が悪性リンパ腫を発症し、余命宣告を受けてからは状況が大きく変わりました。当時いろいろ考えた末に介護離職をすることになったのですが、そこからは同年代の人たちのメインストリームからは外れた人生を送っているという感覚になりました。23歳からケアが終わるまでの約10年間は、社会との接点も持ちづらく、孤立していたと思います。

ー数年前まではヤングケアラーといった言葉は知られていませんでした。自分の置かれている状況が周りとは違う、という実感が強くなったきっかけなどはありましたか。
学生時代は、「家が大変だから家のことをしている」という認識で、ケアをしているなんて大層な意識はありませんでしたね。相手がおじいちゃんとかおばあちゃんなら「介護」と連想しやすいですが、体がしんどくて寝込んでいる母の身の回りのお世話をしたり、ご飯を作ったりといった日常のことなので、特別なことをしているという意識もなかったです。
ただ、「私はなんで毎日こんなに疲れてるんやろう」って思ってました。高校時代はとにかく体がしんどくて、食欲もなかったので昼食はカロリーメイトと水で済ませることが多かったです。大学時代は、周りのみんなが自由な時間を謳歌しているのがわりとカルチャーショックでした。家にすぐ帰るので「付き合いが悪い」とか「家好きやな」と言われたりすることもありました。
母のケアが終わって、後に初めて一人暮らしをしたのですが、その時、24時間が全てが自分の時間であることを実感して、部屋で一人で泣きました。「大学生のあの時、みんなはこんな自由を味わってたんやなぁ」って。
ー当時はどういう支援やサポートを受けられたんでしょうか。
うちの場合は母が指定難病だったので、医療分野の支援、たとえば高額療養費の控除などを受けていました。あと、母が肺疾患になった後に身体障がいの認定を受けたので、自立支援でヘルパーさんに来てもらったりはしていました。
当時、私自身がヘルパーさんに状況の大変さなどを相談するといったことは全くなかったですね。そうした支援はあくまで母親のために入ってくださっていると思っていたので。
今ようやく現場レベルでもケアをする家族はどうか?という家族への目線が入ってきていると思いますが、私の時は、若いししっかりしてるからお世話するには打ってつけ、みたいな感じで、「娘さんがいてよかったね」と周りからは言われていました。現場に入っているヘルパーさんも比較的年配の方が多かったりしますから、見方によっては、若い娘がケアをしているのは自然なことに映るんだろうなと思います。
ケアしているのが幼い子どもだったりしたら周りもどうにかしてあげなきゃと思ったのかもしれません。でも10代、20 代で家のことってなると、お母さん思いのいい子、で終わってしまうことがほとんどではないでしょうか。ジェンダー的な切り口でみると、これが息子だったらまたちょっと反応が違ったんじゃないかなとは思いますね。

ーケアについて、何かポジティブに捉えられることはありましたか?
自分の経験を、必要以上にネガティブだともポジティブだとも思っていません。ただ、母と一緒に過ごせた時間は、本当に幸せだったと思っています。
私の母親は、めっちゃ頑張る人だったんですよ。母は10年以上酸素を吸入しながらの生活で慢性呼吸不全だったので、自由もないし、何より健康な人には想像もつかないほどしんどい毎日だったと思います。それに進行性の病気なので、いつ何時悪化して命を落としてしまうかもしれないっていう恐怖が常にある中でも、母は太陽みたいに明るくて愛情深い人でした。もちろん人間なので落ち込む時も弱音を吐く時もあるけど、よく冗談を言ったり、家族や周りの人を励ましたり、「病気には負けてたまるか」という気概を持っていました。
私も、母の前で「もっと自由に生きたい」とか言ってクヨクヨしたこともあるし、母自身も娘や家族に迷惑をかけているとずっと悩んで苦しんでいました。でも、それでも母は家族が大好きで、1分1秒でも長く生きようと努力し続けていたんですよね。それに私たちが応えないわけにはいかないじゃないですか。
母と過ごす時間の中で、本当の意味で「生きる姿勢」というものを見せてもらった。だから、正直ケアが終わった時はもう私の人生、これでいいかなと思ったんですよ。多分私の人生の中でこんなに哀しくて、こんなに幸せな時間ってもうないだろうなと思ったから。
ー現在、高岡さんは全国での講演活動含めヤングケアラーに向けてたくさん発信をされています。そのモチベーションはどこからくるのでしょうか。
正直、私自身が自発的にこういう活動をしたいと言い出したことはほとんどなくて、全て周りの方にいただいたご縁なんです。ケアが終わった後、目の前には何もない状態でした。もう私の役割は終わったというか、生きている意味がないという気持ちになったこともあります。
家族は、大変だったことはもう忘れて違う人生を歩めばいいと、これまでの人生とは関係のない仕事を勧めてくれたりしました。でも、私は自分の性格上、これまでの自分をなかったことにはできないなと思ったんです。張り合うわけではないのですが、社会人経験も乏しい自分が、同年代の人たちが積み上げてきたものを発揮している場所に肩を並べて入るなんて到底無理です。そうなると、自分がやってきたことを良いかたちで誰かや何かに還元できたらいいなと考えました。
その後ありがたいことに講演や支援にかかわる機会をいただいて。せいいっぱい心を込めて講演を重ねていくうちに、「自分だけじゃないと思えた」「今日ここへ来てよかった」と言ってくださる当事者の方と出会ったり、私の何かを読んでくれた方が「これまで生きてて良かったと思えた」と伝えてくださる機会をいただいたりすることが増えました。私にとって魂が震える瞬間です。
「自分だけじゃない」っていう安心は、私がずっと欲しかったものなんですよ。でもその時私は得られなかったものだから、今、過去の自分に手渡ししているような思いでいます。それを皆さんが受けとめてくださっている感じなんです。だから、私は過去の自分みたいな人に届ける思いで伝え続けると決めています。こんな人もいるんだと思ってくれるだけで嬉しいし、誰かがほっと安心できるような一瞬になれたらっていう、その思いだけでやっています。

ーお話を伺っていると、お母さんがやっていらしたことを今、高岡さんが実践されているという気がしてきました。今後はどのような展開を考えていますか。
それは嬉しいです。私は自分にはほんの小さなことしかできないと思っているんです。自分の思いを広げてしまうとブレるのがわかっているし、正直自己開示はしんどいこともたくさんあるから発信活動もいつやめてもいいと思っているんです。でも、不思議なんですけど、いつやめてもいいと思えば思うほどご縁は広がったりするんですよね。
そうやって活動を続けていたら、これってヤングケアラーだけの問題じゃない、と思うようになりました。
ケアにしても、それが半年とか 1 年で終わればまた違うかもしれないけれど、24 年って結構長いですよね。母が病を患って、私は子どもの頃からずっと精神的にも休まらなかったし、そういう安心できない状況が慢性的に続くのは、結構リアルに人体に影響していると感じています。
子どもは身体も心もまだまだ発達途上。だからこそ、子ども時代に定着した不安定さを大人になってから克服するのは至難の業だと思うんです。暴力や虐待といった、特別にショッキングな出来事じゃなかったとしても、そうした日々のストレスや不安を感じる一日の積み重ねが、子どもの将来を作る土台になっていくわけなので。
だから今は、子どもが安心を感じつづけられるような社会になるためにどうしたらいいか、を考えながら、教育や啓発など、何かしらに関わっていけたらなと思っていて。そのためにもいろんな方と繋がって勉強しながら、私にできることでちょっとずつ展開していけたらなと思っています。

高岡里衣(たかおか・りえ)
9歳から24年間、難病の母と伴走してきた元ヤングケアラー。現在は、ケアと自己実現の両立に悩んだ経験から全国各地で講演、執筆活動を行っている。また京都・大阪・東京を中心に、行政機関や民間団体を通じてヤングケアラーの支援活動にもかかわっている。共著に『ヤングケアラー わたしの語り』(生活書院/2020年)。