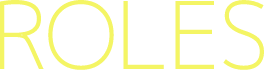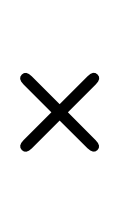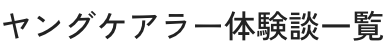記事一覧
記事一覧
 【#2】 ケアの中のふとした「めっちゃおもろい」瞬間を分かち合うことが、自分の人生を楽しく生きることへとつながっていく。冠野真弓さんが編み出した「ラフィングケアラー(笑っているケアラー)」の考え方とは
【#2】 ケアの中のふとした「めっちゃおもろい」瞬間を分かち合うことが、自分の人生を楽しく生きることへとつながっていく。冠野真弓さんが編み出した「ラフィングケアラー(笑っているケアラー)」の考え方とは

【#2】 ケアの中のふとした「めっちゃおもろい」瞬間を分かち合うことが、自分の人生を楽しく生きることへとつながっていく。冠野真弓さんが編み出した「ラフィングケアラー(笑っているケアラー)」の考え方とは
2025.01.27
家族のことを隠してきた10年間を経て、大学の友人や先生の支えから「きっと大丈夫。なんとかなる」と思えるようになった冠野真弓さん。人が大好きなことや家族の病気の経験から看護師になり、その後「精神疾患の親と暮らす子ども」「ヤングケアラー」という概念と出会って衝撃を受けます。自分を体現する言葉はないかと考えて作り出した「ラフィングケアラー(笑っているケアラー)」について、詳しく伺いました。
(#1はこちら→https://youngcarer.or.jp/ycmedia/interview/1286/)
家族看護学会でのヤングケアラーとの衝撃的な「出会い」
看護師になり、「これは天職だ!」と思って働いていたところ、今度は自分が初めて入院する経験をしてしまいました。原因はわからなかったのですが、初めて患者さん側になって、健康な人との隔たりを感じたというか、薄いベールを1枚かけられたような感覚で、「私、あっち(健康な人)側には戻れないのかもしれない……」と思いました。
また、この時に、「ケアとの心理的な分離」も経験しました。「家族の面倒は私が看る!」「私は看る人なんだ!」って思ってきたけれど、もしかしたら私はもう看ることができないのかもしれない。自分のアイデンティティを失ったような感覚でした。
検査入院から仕事に戻っての1年くらいは、患者さんを受け持たず、医師とのやり取りや、スタッフの業務調整をするリーダー業務だけさせてもらいました。ちょうど、その数年前からお父さんがパーキンソン病になっていたので、いつか実家の近くに帰らなきゃなという思いもありました。これからどうしようと思っていた時に、看護大学で教育に関わらないかと声がかかりました。私はいつも「今だからこそ選択するものは何かな」と考えています。その時々の流れを読むというか、感じるようにしています。お母さんの病気があったから看護師になる、というような選び方をしてきたから、「いま臨床が難しいからこそ教員になる」というのが、私に来ている流れなんだろうなと思いました。
そして、大学教員として、研究テーマを模索していたところ、2018年の家族看護学会で衝撃的な出会いを果たしました。「障がいと共に生きる家族を支えて ――精神障がいの親と暮らす子どもへの支援から見えてきたこと」という演題でした。この発表をされた先生は、2009年に精神障がいの親と暮らす子どもを支援する会を立ち上げられた方です。大きなホールで先生の発表を聴きながら、「この研究発表、私のことが書いてある!」と思いました。私が感じてきた思いを明確に言語化してある先生の言葉1つ1つが、私のモヤモヤした思いを代弁してくれていると感じて、この人につながりたいと思いました。そこから先生がされている活動を調べて、「精神疾患を持つ親と暮らす子ども」の全国集会へ行って、初めて同じ立場の人達とつながることができました。「分かる分かる!」っていう感覚で家のことを話せる人たちにつながれたのは衝撃でした。「みんないままでどこにいたの?こんなにいたのになんで今まで出会えなかったの?」と思いました。この出来事が、「ヤングケアラー」という言葉を知ったきっかけでした。
つまずいても立ち上がる、自分のあり方を体現する言葉が「ラフィングケアラー」
私は精神疾患を持つ親と暮らしてきた子どもの立場でもあるし、きょうだいの立場でもあります。そして、いまは神経難病の疾患を持っている家族の立場でもあります。緩和ケア病棟での勤務以後はがんサロンやグリーフケアの会にも関わり、つながることが人の力になっていくことも感じました。色んな立場を持っていることも自分の強みだと感じたので、私は疾患や立場に特化せず、ヤングケアラーさんやケアラーさんとつながりたいなと思いました。そんな活動をイメージしたときに、自分のあり方を体現する屋号としてつくったのが「ラフィングケアラー」でした。
「ラフィングケアラー」というのは言葉の通り「笑っているケアラー」で、楽しんだりおもしろがりながら家族のお世話をしているケアラーのことです。精神疾患の親と暮らす子どもの集いに参加した時に、ご自身もしんどくなっていたり、体調を崩している方とたくさん出会いました。その時、自分の「ヘラヘラ力」という強みに気づいたんです。ケアの中でもおもしろい部分を見つけたり、楽しい方向に捉え直しているなと思いました。それは、自分の情緒を安寧に保つため、心と身体の健康を守るためにしてきたんだと思います。
ケアの話は、「辛い・暗い・しんどい」というマイナスの側面に焦点が当たりがちです。能動的ではなく受動的に人生が巻き込まれていくようなイメージが強いですよね。でも、ケアの中には、「学びや成長・日々のすべらない話」というプラスの側面もあると感じています。特に、”すべらない話”に目を向ける、気づくことは大切で、ケアの瞬間瞬間は苦しさだったり、「えらいこと起こったな……」みたいな絶望を感じる時もあるけれど、笑いにまで昇華できたら最強だなと思っています。さらにはそれを言えるフィールド、一緒に笑い合える自分だけのフィールドを作っておくことが大切だと感じています。家族のことを自己開示しておくことで、”すべらない話”があったときに「ねぇ、聞いてこんなことがあって……」となんのハードルも、病気の説明もなくネタとしてすべらない話ができる。一旦つまずいても立ち上がる、安心や笑いに着地しにいくのが、ラフィングケアラーなんです。
緩和ケア病棟の看護師として働いていた時に知ったのが、アルフォンス・デーケン先生(死生学の教授)がおっしゃっていた「ユーモアとは、にもかかわらず笑うことである」というドイツのことわざです。患者さんに関わる時に、しんどい日々の中でも、クスッと笑える時間を共有したいと思っていました。 緩和ケア病棟におられる患者さんは死に行く人ではなく、最後まで生き切る人なので、一緒に笑い合いたいし、一緒に生きていたい。死を待つ時間ではないので、今日一日何か良いことあるかな、ほっとする時間あるかな、どう楽しく一日を過ごすかを考える、それがその後のラフィングケアラーの考え方にもつながっていると感じています。
人って希望がないと生きていけないんです。だから、笑うんです。

支援者として大事なことは「Not Doing But Being」
ヤングケアラー支援者として大切なことは、何もできないということを知っていながらも何かできることはないかと模索し続けることだと思っています。何かを前のめりでしようとしないこと。「にもかかわらず笑う」と同様に大事にしているのが、シシリー・ソンダース先生の「Not Doing But Being」という言葉です。これも緩和ケア病棟時代に学んだ言葉です。緩和医療は、根治目的ではなく、症状緩和を主な目的としています。いろんな苦痛症状が出てきた時に、薬剤やケア、人というつながりの中で何かできることはないかを考えていきます。一見、医療では何もできないと感じられるような場面も多々あります。決められた痛み止めの量や使用間隔を超えてまでは提供できないし、例えば患者さんから「いま生きていることに意味を見出せない」「命を終えたい」と言われてもそれを手助けすることはできません。だけれども、それでも何かできることはないかを考え続け、何もできることがないからと言ってその方のベッドサイドに行く足を遠のけるのではなく、だからこそそばに行く。何もできないかも知れないし、何かできるとおごらず、できないことを知っていて、関わり続けるんです。「Not Doing But Being(何もできない、でもそばにいる)」について、シシリー・ソンダース先生は、「支援者として何もできない時があると知り、何かをするではなく、ともにあり続ける、ただあり続ける、一緒にあり続ける」ことだと言われています。だから、私が患者さんに関わる時も、自分が何かできるとは思わずに、でも何かできることはないかとアンテナを立てて関わり、「あなたのことを気にかけています」「あなたに関心を寄せています」と言葉や態度で伝えています。何か劇的に改善するとか、その人の苦しみをゼロにするなんてできないことを知っていながらも、関わり続けるんです。これはヤングケアラー支援においても言えることだと思っています。
そして、私が講演の時に挙げている支援者に求める3つの力として、「想像力」「質問力」「傾聴力」があります。私は「誰にも話すもんか時代」に、同級生に悟られてはいけない、隠さなければと思っていたので、いつもヘラヘラ大丈夫なふりをしていました。そしたら「カンちゃんって悩みなさそうだよね」と言われることが多かったんです。この言葉を聞いて、上手に隠せているんだと安心したこともあった一方で、グサッと傷ついたりもしました。だからこそ、支援者には想像力が必要で、見ようとしないと見えない存在がいるんだと、大丈夫そうに見えるその子にも何かあるかもしれないという視点を忘れないでいただきたいと思っています。
また、別の視点の想像力としては、「変わるのは怖い」ということも知っていてほしいです。それがあるかないかで提案の仕方が変わってくるだろうなと思います。人ってそれがどんなに「良い方に変わる」と思っていても変わるのは怖いんです。例えば、自分が望んで転職するにしても、変化には絶対に勇気がいります。いざ、そこになじむまでは毎日緊張が伴いますよね。私が普段働いている訪問診療や訪問看護、ヘルパーなど在宅支援を届けるときも、何度も必要性を伝えてやっと受け入れてもらったり、導入したけど一旦ストップしたり。人は変化に敏感で、その変化にすら対応する力が残っていないときもあるんです。だから、それを知って支援を差し出してほしいと感じています。
質問力は、相手の文化や歴史を知ろうとすることです。家族にはその家族だけの文化や歴史があります。それぞれの¨当たり前¨や¨普通¨があるんです。それを否定するのではなく知ろうとする。聞き出すのではなく、あなたに関心を寄せているということが伝わるように信頼関係の構築につながるような質問をなげかけていくことを意味します。
最後に傾聴力は、相手が「分かってもらえた」と思うような聴き方をすることで、相手の話を一旦「分かった」と飲み込む力のことです。ただ聞いてればいいわけではなくて、相手が「そうそう!わかってくれてるな」と思えるような相槌や眼差しを向けながら¨聴く¨ということです。
種まきしただけで芽吹いていくような、ラフィングケアラーのコミュニティを作りたい
私はたくさんの人との出会いに救われてきました。人に恵まれていると感じることが多いです。患者さんからもたくさんのことを教わってきました。緩和ケア病棟で出会った90代の男性患者さんとのやり取りは今でもよく思い出します。フランクルの「夜と霧」という本を原書で読むほど本が大好きな、¨本の虫¨な方でした。ある夜見回りをしていると寝つけないようで、しばらくその方のベッドサイドに座り、お話をしました。色々話していると、特攻隊にいた時の戦争体験のお話になりました。結婚したばかりの友人が胸ポケットに奥さんと生まれたばかりの赤ちゃんの写真を入れて出撃し、その方は亡くなられたというエピソードでした。そして、生涯結婚をしなかった自分が生き残って、守るものがあった友人が亡くなったと。その体験とフランクルの本から、「人ってなんで自分が生きてるんだって人生に問いかけるだろう。でも、そうじゃないんだよ。人はね、大きな流れの中で生かされてるんだよ。人生の方から問われているんだよ」と教えてくださいました。私はフランクルの夜と霧を知ってはいましたが、目の前にいる90数年生きたその方が人生を通して語ってくださる言葉だからこそ、その言葉がスッと入ってきました。「なんで生きてるんだ」ではなく、「私たちは大きな流れの中で生かされている」んです。
私自身は、いつも「これがあったからこれがある」という考え方をしようと、行動してきました。「家族の病気があったらから天職と思える看護師になれた」というように。そして、臨床が難しいと感じた体調変化のタイミングで大学教員になったからこそ、研究テーマを模索する課程で「ヤングケアラー」という言葉を知って、ピアサポートにつながり、自分を体現するラフィングケアラーに辿り着きました。ネガティブな出来事があった時に=(イコール)不幸になっていくのではなく、その出来事をどう捉えるか、意味づけしていくかだと思っています。
今後は、自分だけでなくヤングケアラーさんやケアラーさんがラフィングケアラーに変容していく場所づくりをしたいと思っています。どんな形とタイミングで叶っていくのか、その時どんな仲間がそこにいるのかは分かりませんが、ラフィングケアラーという言葉のもとに集うコミュニティなので、上下関係でなく、それぞれがそれぞれのパワースポットになっていけるような、相互的な形のコミュニティを作りたいです。その目標は、ケアラーさんたちが手持ちのカードで幸せになって、だれかの言う幸せの形ではなく、自分だけの幸せの形を見つけることだと思っています。
ヤングケアラーさんは、子どもの頃から家族のことを優先してきたので、自分の本当の声が聞こえなくなってる人が多いと感じています。だから、そのコミュニティが自分の本当の声を聞くというところに立ち返っていける場所であれたらと思っています。
もちろん、すべらない話もしたいです。つらいことがあっても「ネタが一つできた!」というようにすべらない視点で捉え直して共有していきたいです。ただただつらいと感じる時間ももちろんあるけど、それも話した上で最後はすべらないところに着地できたらと思います。そういう視点に自分で気付いて、楽になったり、1人じゃできない時は誰かが「前はこれを心配してたけど大丈夫だったね。良いこと見つけたよ。」って、お互いの状況を俯瞰する視点をもって伝えていけるような場所でありたいですね。一人でケアをしていると、なかなかそうやってケアを認識できるタイミングがないから、ラフィングケアラーのコミュニティでは「にもかかわらず笑う」という時間を共有できるようにしたいんです。
ケアラーの特性上、対面では集まるのが難しい人がたくさんいるから、まずはオンラインで集まって、その後は全国でそれぞれで集まっていくみたいな、そんな方法が現実的なのかなって思っています。今はその種まき期で、ラフィングケアラーっていう言葉をお届けしていく。そういう視点があるんだって気づいた人達は、ちょっと種まきしただけで、芽吹いていって、その芽吹いていった人たちで一緒に集まって、いろんなところにいっぱい花が咲いていったら素敵だなって思っています。

冠野真弓(かんの・まゆみ)
大学卒業後、混合内科・CCU(循環器の集中治療室)・緩和ケア病棟などの看護師として病院勤務を経験。看護系大学の教員を得て、現職である在宅診療専門のクリニックの立ち上げに関わる。ヤングケアラー啓発支援団体K&の代表としてインスタライブで発信や講演依頼に応じて活動中。今後の野望はヤングケアラーさんやケアラーさんがラフィングケアラー(笑っているケアラー)に変容していく場所づくりである。