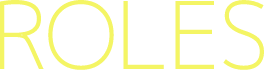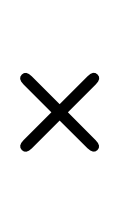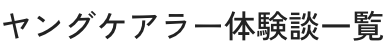【#1】 9歳のひな祭りは「お母さんが壊れた日」。統合失調症の母のことを話してはいけないと思っていた冠野真弓さんが、「誰にも話すもんか時代」からケアについて話せるようになるまで
2025.01.27
岡山県で暮らす冠野真弓さんは、幼少期から統合失調症の母を、高校生以降は父と姉のケアもしてきました。現在は、3人のケアを続けながら看護師として働いているほか、ヤングケアラー啓発支援団体の代表も務めています。ケアの経験や葛藤、自分の人生における自信につながった出会いなど、冠野さんのこれまでについて伺いました。
自分がしてもらってうれしかったことを思い出しながら、お母さんの背中をトントンした
9歳の時、私が小学校から帰って来ると、お母さんとの会話が急に通じなくなっていて、そわそわと落ち着かず視線も合いませんでした。家の中で暴れる様子もあったので、夜間病院に大人3人がかりで連れて行き、そこから数か月間、お母さんとは離れ離れで暮らしました。お母さんを病院に残してきたその夜、家に戻ると、床にコロンってひなあられが転がっていて、「お母さん、途中までひな祭りの準備をしてたんだ。でも今は絶対そんなのわかる状況じゃない」っていう強いコントラストが、「お母さんが壊れた日」である3月3日の映像として鮮明に記憶に残っています。それまでのお母さんは、お料理やお菓子作りもすごく上手で、洋服や着物も作ってくれる“主婦の鑑(かがみ)”と言われていた人でした。そんな私の中で完璧だったお母さんが、その日突然壊れたっていう……。
当時、お母さんがどうなったかは何も聞かされておらず、漏れ聞こえてくる大人同士の会話から情報収集していました。お父さんが「身体の病気だったらな」と言うのを聞いて、「身体以外に病気があるんだ」って思いました。後になって統合失調症と知りましたが、当時はインターネットが発達していなかったから自力で情報も集められませんでした。
数ヶ月経って戻ってきたお母さんは、全然元通りではなくて、 家の中をハイハイしたり、カラスが鳴いたら「合図だ!」と言ってベランダに駆け出して行ったりすることも。お父さんが仕事から帰るまでの数時間をお互いがどう安全・安心に暮らそうかと考えていました。誰かが対応の仕方を教えてくれるわけでもなかったので、自分で試行錯誤するしかなかった当時が、ケアのスタートだったのかなと思っています。物音に気をつけるとか、このテレビ番組をこのまま見つづけたら衝撃映像が流れそうと思ったらチャンネルを変えるとか、テレビのボリュームに気をつけるとか。お母さんの興奮につながらないように、お母さんが怖がらないように、つまづきそうな石ころを避けて避けて避けて……、と先回りする感じの生活でした。
ただ、同時期に看護職を目指すことにつながったケアの原体験とも言えるエピソードがあります。それは「誰かが殺しに来る」という幻聴におびえているお母さんをなんとか落ち着かせたことです。自分の9年間の人生の中にある知識を総動員して、自分の膝の上にお母さんを座らせて、背中をトントンってしたんです。それは自分がお母さんにしてもらって好きだったこと、落ち着いた気持ちになったことでした。自分がまだ幼かったころ、寝付けない時にお母さんに背中をポンポンってしてもらうのが好きだったから、それを思い出しながら同じくらいゆっくりしたペースで優しく背中をたたきました。そうすると私の腕の中でお母さんがふぅっと安心した様子になり、「すっごい上手くいったぞ!」って自己肯定感も爆上がりしました。「この病気って薬や手術ではすんなり治らないこともあるけど、うまいこと対応したらこうやって落ち着くんだ!」と思えた体験でした。環境要因である家族が上手に対応したら落ち着くんだというこの時の成功体験は、魔法の杖を1本手に入れたような気分でした。
お母さんのケアに関しては試行錯誤でしたが、こうした成功体験を積み重ねていくことで、何かびっくりするようなことが起こっても、その波に乗ってやり過ごしたり、溺れないようにプカプカ浮かんだり。たまに大波が来て、ちょっとこれは越えられないかもという時もありつつ、徐々にコツがつかめてくるんです。大学に入り、人に話せるようになってからは、だいぶ楽になりました。ケアの知識と、話せる人が増えていくことで、どんどん生きやすくなりました。
「誰にも話すもんか」と思っていた自分を支えたのは、先生からの何気ない一言。
小学校6年生になるタイミングで広島から岡山に引っ越したのですが、その引っ越しがすごく嫌でした。あと1年で卒業なのに、大好きな学校から離れなきゃいけない。でも、お母さんの幻聴と近所の人の目から地域にいづらくなり、お父さんが転勤願いを出したというのが引っ越すことになった経緯だったから、お父さんの気持ちもわかる。お父さんの苦しそうな姿も見てきたから、私が嫌だと言えるような状況でもないし、「足を引っ張っちゃいけない」と思っていました。
転校前、担任の先生に「友達には私が引っ越すことを言わないでほしい。私のタイミングで友達に話すから」と口止めをしました。その時、先生にどこまで家のことを伝えられたかは分からないけど、「実はお母さんが……」と事情を話したら、先生は私に「今度2人でお出かけでもする? なんか美味しいもんでも食べに行こっか!」と言ってくれたんです。もしかしたら他の先生の間でも情報共有はされていたかもしれないけれど、大変だね、頑張ってるね、かわいそうだねと哀れな気持ちを向けられるでもなく、大事(おおごと)にされるわけでもなく、「なんか美味しいものでも食べに行く?」というまるで友達にでもかけるような、その言葉がすごく嬉しかったです。本来は先生が言える言葉じゃないかもしれないけれど、表面的ではなく本当に関心を寄せてくれているというのが伝わる言葉かけでした。その先生とは転校してからも年賀状のやり取りを続けていました。
この時の先生の言葉が、大学に入り、友達に家族3人のことをすべて話せるようになるまでの「誰にも話すもんか時代」の10年を支えてくれました。私が孤軍奮闘しているこの状況をたまに思い出してくれる人、関心を寄せてくれる人、知っててくれる人がいるっていうことが救いでした。そこからどんなアクションがあるとかじゃなくても、ただ自分の存在を知っててくれる大人がいることが救いだったんです。
中学生の時、同級生とアイドルの話で盛り上がっていたら、そのアイドルがうつで休業になったんです。そうしたら、友達が「うわっ、うつで休業だって気持ち悪っ!」と言ったんです。私はその言葉を聞いて震え上がりました。うつ病で「気持ち悪い」って思われるなら、お母さんはどうなっちゃうんだろう。当時はまだ、統合失調症ではなく名称変更される前の精神分裂病と呼ばれていた時代で、「精神が分裂って、どうなっちゃうの?」という怖い印象のある言葉でした。それと比べれば、私の中でうつは怖くない言葉だと思っていたので「世の中の人はうつでそんな反応するんだ。じゃあ、お母さんのことバレたらどうなっちゃうんだろう・・・」と思いました。それまで大人の様子から話さない方がいいことなのかなと思っていたところから話さないことが家族を守ることなんだという認識になり、誰にも話すもんか時代に突入するきっかけとなりました。
今振り返った時に、当時の自分を表すのにぴったりだなと思ったのが「カオナシ」。いっぱい飲み込んで、飲み込んで、最後にどろ~って自転車とかいろんなものがたくさん出てきますよね。私も当時、いろんなことを飲み込んで、とりあえず自分の中に抱え込んでいました。

話すことで、味方・理解者ができる。なんとかなるという自信がついた大学時代
「誰にも話すもんか」と思っていた私が、話すことへの意識をガラッと変えることができたのが大学時代でした。それまでは、お母さんのことで近所の人にも避けられて居づらさを感じたり、排除される感覚があって「隠さなきゃ」と思っていました。でも、初めて話した相手が自分が想像していたよりも”普通“に聴いてくれて、一緒に悩んだり考えたりしてくれたことで「話すことで味方や理解者ができる」と思えるようになりました。
私が中学生~高校2年生くらいの間は一度お母さんの症状がすごく落ち着いていました。なので私が高校に進学した頃からお父さんが単身赴任をしていたのですが、高校2年生の夏ころからまた調子を大きく崩してしまうタイミングがやってきました。そこからは、大学卒業まで、お母さんだけでなく精神的に不安定なお姉ちゃんも私がひとりで看ていました。大学受験も加わり、いっぱいいっぱいになって初めて人に家のことを全部話すというタイミングがやってきました。入学したのが看護学科というのも大きかったと思います。
大学1年生の時、同じ看護を目指す人なら精神疾患の人もケアの対象なので、気持ち悪いという感情以外で聴いてくれるかも知れないと思って、2人の友達に話しました。最初に「今から一見重そうな話をするけど、重く受け止めないでほしい」と伝えてから話しはじめました。私の中では号泣しながら喋った記憶があったけど、友達には「 淡々とすごいこと喋ってた。最後に泣いてたよ」と言われて、 相手もただただ聴いてくれました。一人は「冠野ちゃんめっちゃ頑張ってるね、これからはもうひとりじゃない、 私がなんとかする」みたいな熱い子。でもそれは鬱陶しい熱さではなく、言葉だけじゃない人っていうのが伝わるから、親身になってくれて嬉しかったです。もう一人は自分の中の物差しがしっかりしてる”ええ塩梅の人”で、私が初めて家族の「すべらない話」をできるようになった相手。私がおもしろおかしく喋っていたら、気遣いながらも「その話おもしろいね」って言ってくれて、精神科看護学の授業でも習わないような家庭でのケアの成功体験やすべらない話をすると、一緒におもしろがってくれました。
大学時代は6人グループで、この6人が知っててくれることで救われました。例えば、お母さんの入院中に付き添いを求められ、お母さんのベッド横に簡易ベッドを置いて寝たり、レポートを書いたりしていることがありました。そういう時間を過ごしていることや、「お母さんが落ち着かなくて離れられないから、ちょっと今日は授業に遅れるね」と本当の理由を言える相手ができました。それがめちゃくちゃ大きかったです。本当の理由を言える相手がいなかったら、ただ遅刻した人になってしまい、周りの目が冷たくて学校に行きづらくなっていたかもしれません。でも、メールで事前に「今日こういう理由で遅れるから後でノートを見せてほしい」って頼ることができて、学校へ行ったら6人グループの子たちが「お疲れ様」って優しい眼差しで迎えてくれたんです。休憩時間になったら、「大変だったね」「あれから家のことはどうなん?」って言ってもらえるのが救いで、その労いや話せる時間があるからこそ学校に行けていたと思います。
また、精神科看護学の最初のレポートで「あなたのバックグラウンドを書きなさい」という課題がありました。私のバックグラウンドとなるとやはり家族のこと。白紙で出すか、それとも家族のことを書くのか悩みましたが、一番受けたかった精神科看護学の授業でもあったので、家族のことを書いて提出したら担当の先生に呼び出されて「あなたの家はどうなってるの?大丈夫なの?」と言われました。家のことを説明したら先生は、「わかったわ。また何かあったら話して」と言ってくださり、家のことを話した後も、話す前と変わらない態度でいてくださり、私は「話しても大丈夫だ」と思うことができました。それ以降は「先生、あれからこんなことがあって……」と言えるようになったんです。
卒論の時にお世話になった別の先生にも助けられました。ある日、お母さんのお風呂上がりに仙骨部に真っ黒なカサブタを見つけて先生に相談したら、「写真を撮ってきなさい」と言われました。後日、携帯で撮った写真を見せたら「褥瘡(じょくそう)だ」と言われたんです。なんとその先生のされている研究が褥瘡研究で、先生は医師でした。先生から「治療方法を教えるから一緒に治そう」と言われ、ラップ療法を教わりました。困ったなっていう時に、意図せず専門家が現れたんです。私はそれをきっかけに、私の人生にはちょっと事件が多めだけれど、ミラクルなタイミングでちゃんと助けが入るようになっていると思えるようになりました。話すことで味方や理解者ができる。多分大丈夫なようにできている。そんな自信につながっていった経験が、私の大学時代には濃縮されています。みんなが糸を垂らしてくれて、「困ったらこれを引っ張ったらいいよ」と言ってくれる人に恵まれている感覚を得ていきました。
家族もまとめてケアするんだという気持ちから、緩和ケア病棟の看護師に
看護師になった理由は、やっぱりお母さんの病気の経験が大きかったです。患者さんの家族ってこんなにも困っていたり大変なんだという実感があり、家族にもケアが必要だと強く思っていました。お父さんの単身赴任中にお姉ちゃんも不安定になり、不登校やリストカット、過換気などの症状で生きづらさが出てきて、大人になってついた診断が発達障害でした。リストカットでちょっと切りすぎた時には、用手圧迫といって手で押さえて止血したり、それでも止まらない時は縫ってもらうしかないので病院に付き添っていました。過換気で倒れた時には、 そばで声をかけたり、背中をさすったりしながら一緒にゆっくり息をして、呼吸が整うのを待ちました。お母さんのこととお姉ちゃんのこと、ケアが身近にずっとあるのが日常でした。
私が高校2年生の夏頃には、お母さんがもう一度大きく揺れ動いてしまいました。ちょうど受験のことを意識するタイミングで、「ああ、もうケアを学ぶしかない」って思ったんです。それまでの暮らしの中から治すのではなく適切な対応の仕方、ケア方法が知りたいと思いました。そう思った時に医師ではなく看護師でした。例えば、お母さんの病気が身体的なものだったら医師が行うような治療に目が向いていたかもしれませんが、最初のケアによる成功体験もあり、精神疾患は生活の中でいかに安心できるように対応していくかだと思っていたので、“治療”という分野より“ケア”だと思っていました。また、当時インターネットがまだ発達していなかったので、病気の知識につながるには専門書を読むしかなくて、対応の仕方を知りたいと思った時に、私の中では看護師一択になっていきました。
自分の家族の経験から、患者さんだけでなく患者さんの家族も困っているということを知っていたので、その経験は看護師として生かせるかもしれないと思っていました。子どもの当時、家族看護という言葉はまだ知らなかったけれど、「病気の人も大変だけど、家族もこんなに大変なんだ。家族が元気じゃないと病気の人にも影響する。家族が元気だとその家族にしかできない本人への関わりでまた本人も安心できる。家族もまとめてケアするんだ!」みたいな思いを持ちつづけてきました。もちろん、そこまで手が回らなくなってしまうような現場の大変さも見てきましたが、ご家族が面会に来た時には意識して声をかけたりすることも気にかけていました。
看護の分野の中で緩和ケアに進もうと思ったのも、 WHOの定義として緩和ケア病棟が家族もケアの対象だと明記されていることに感動したからでした。
看護師は特性上、いろんな家族、いろんな病気の人、いろんな人間に深く関わるじゃないですか。人の人生に深く関わることで、感じるようになったのは、「大変なのは自分だけじゃない」ということ。人それぞれいろんな困りごとがあって、でもそれをみんな前面には出さず、見えないようにしながら生活している。困っていないように見える人も、実はそれぞれ困り事を抱えながら、それぞれの持ち場で一生懸命生きているということを実感しました。
#2(https://youngcarer.or.jp/ycmedia/interview/1301/)へ続く
冠野真弓(かんの・まゆみ)
大学卒業後、混合内科・CCU(循環器の集中治療室)・緩和ケア病棟などの看護師として病院勤務を経験。看護系大学の教員を得て、現職である在宅診療専門のクリニックの立ち上げに関わる。ヤングケアラー啓発支援団体K&の代表としてインスタライブで発信や講演依頼に応じて活動中。今後の野望はヤングケアラーさんやケアラーさんがラフィングケアラー(笑っているケアラー)に変容していく場所づくりである。