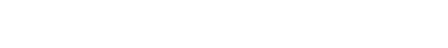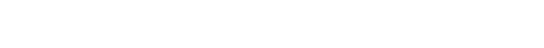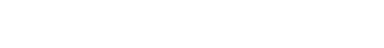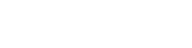「親を支えてきた子ども同士だからこそ話せる」支援者が見守る当事者の輪

親の介護や家事など、本来なら大人が担う役割を、日常的にこなしている子どもたち。しかし、彼らの存在はまだ社会で十分に認識されていません。そんな中、2024年6月の法改正により、ヤングケアラーが公的な支援対象としてようやく明記されました。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」では、ヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義。支援対象は18歳未満に加え、進学や就職など人生の大事な選択を迎える若者にも広がりました。
では、ヤングケアラーが安心して過ごせる社会をつくるには、なにが必要なのでしょうか。今回は、「精神疾患の親をもつ子どもの会(こどもぴあ)」の設立支援や、著書を通じてヤングケアラーの実態を発信してきた横山恵子さんにお話を伺いました。子ども同士が繋がる「ピアサポート」の場づくりや、支援者が静かに寄り添う大切さについて考えます。
【 ピアサポートとは? 】ピア(peer)は「なかま」を意味し、ピアサポートは「仲間同士で支え合うこと」を指します。ピアサポートの場では、「同じ立場だからこそ安心して話せる」「似た経験を聞くことで心が楽になる」「これから先の人生の参考になる」といった声がよく聞かれます。出会い、語らい、体験を共有することで「一人ではない」と感じられ、似た経験の仲間から知識や対処法を得ることもできます。安心・安全な場をつくり、仲間と繋がることを大切にしているのがピアの場の特徴です。 |
【 こどもぴあとは? 】「精神疾患の親をもつ子どもの会(こどもぴあ)」は、現在全国7カ所に展開されています。同じ立場の人同士が語り合える場を提供しながら、支援者への発信も行っています。精神疾患の親がいる子どもたちの多くは、子ども時代にヤングケアラーとして家族を支え、大人になってからも生きづらさを抱えることがあります。そうした背景の中で、子どもたち自身が仲間との繋がりを求めたことをきっかけに、こどもぴあは生まれました。未診断のケースでも、精神疾患の親を持つ子どもであれば参加可能です。活動には、10代後半から上の世代まで、さまざまな年齢層が参加しています。 |
「あくまで主役は子ども」支援者が一歩引く大切さ
―― 本日はお時間をいただき、ありがとうございます。横山先生は、精神疾患の親を持つ子どもたちについての著書を多数執筆され、こどもぴあの設立も支援されています。まずは、ピアサポートグループの立ち上げや支援に取り組むようになったきっかけを教えてください。
もともとは、精神障害者家族会の活動に関わり、家族会の運営や、そこに参加するご家族の支援をしていました。家族会の参加者は主に親の立場の方々ですが、関わらせていただくうちに、精神障害者家族には親だけでなく、きょうだいや配偶者など、さまざまな立場の方がいることに気づきました。
そして最後に見えてきたのが、子どもの立場の方々です。彼らは、同じ立場の仲間と繋がりたいと願っていました。そこで、以前から家族会で使っていたプログラムを活用して、「子どもたちが語り合える場を作ろう」と決意したんです。
2015年から子どもの立場の家族学習会を開き、3年後の2018年1月に、そこで出会った仲間たちと「こどもぴあ」を設立しました。代表と副代表は、20代の若者たちが務めてくれたんですよ。設立当初、新聞社の取材記事が全国版に掲載され、たくさんの仲間が写真に写ってくれて……。「スティグマ(偏見)の中にいる家族だけど、子どもを通して社会が変わるかもしれない」と希望を感じた瞬間でしたね。
―― こどもぴあは「精神疾患の親をもつ子どもの会」として、子どもの立場の方々が集まる機会を定期的に提供していますよね。本日のインタビューでは、冒頭にこどもぴあの副代表である小林鮎奈(こばやし あゆな)さんも同席してくださっています。
(小林)横山先生の家族学習会に参加したことがきっかけで、こどもぴあの副代表をさせていただくことになりました。ただ、初めての経験だったので、最初は主体的に前に出ることができなかったんです。そんな私たちを見て、横山先生は何度も「みんなで作る場だよ、自分たちで考えて作っていいんだよ」と安心させてくれました。「子どもの立場の人たちで協力して語りの場を作るにはどうしたらいいか」というところから、いつも一緒に考えてくれて……。出会った時を思い出すと、本当にありがたかったなぁと、あらためて感じますね。
(横山)こちらこそ、小林さんたちがこどもぴあの代表や副代表になってくれたこと、とても感謝しています。家族学習会への参加を通して、素晴らしい仲間との出会いと繋がりが生まれたことが、こどもぴあを立ち上げる原動力になったと思っています。

―― こどもぴあ設立にあたり、横山先生が意識した点や注意したポイントはありますか?
(横山)活動の軸を子どもたちに置き、一歩引いたサポートをすることを意識しています。会の主役は支援者の私ではなく、子どもたちですから。
また、支援者や研究者にありがちなのは、目的の達成後に手を引いてしまうこと。家族会のような自助グループは設立も大変ですが、それ以上に難しいのは、活動の継続だと思っています。支援者が先頭に立つのではなく、グループの成長に応じて、支援のあり方を変えていくことが必要なんじゃないでしょうか。
こどもぴあの設立を支援した者として、これからも活動が継続できるよう、側面的に寄り添う支援を継続していきたいですね。なにより、こどもぴあに関わらせていただくことで、たくさんの学びをもらえますから……。活動を支援するのは、自分のためでもあるんです。
―― ご自身が主役にならないよう、あくまで黒子の立場で伴走しているんですね。
(横山)そうですね。活動の中で「あなたがいるからやっていける」と感謝されると、確かに喜びを感じます。でも、そういう関係はメンバーの力を奪ってしまうので……。できるだけ後ろに下がるようにしているんです。ときには前に出て話すこともありますが、それは外部の方や新しい参加者に対して、この会の信頼を担保する役割だと自覚しています。
メンバーが「自分たちの力で活動できている」と思えなければ、会の力は本当には育ちません。私にできることは、あくまでサポート。「大丈夫、みんなの力でやれてるよ。自信を持って!」とメッセージを送りながら、今後も陰で支えたいと思っています。
―― 前に出るところ、後ろに下がるところ、柔軟に対応していることがよくわかります。
(横山)子どものピアサポートグループはまだ少なく、こどもぴあには大きな期待が集まっています。行政や支援者からの体験談の依頼や、研究者や学生からの研究協力のお願いも多く届きますが、みんな「自分の体験が役立つなら」と積極的に協力してくれて。
だからこそ、ヤングケアラーの立場を経験した方たちが声を上げ、行動していることをきっかけに、ケアラー全体の問題について考える機会にしたい。私が依頼された研修会では、なによりも「当事者の体験を聴くことが大切」と伝えています。また、ヤングケアラー支援や家族支援の研修会では、必ず子どもの立場の方や、親・きょうだいの立場にある方たちに同伴してもらい、実際の体験談を話していただくようにしています。
現在の大学教員としての役割を活かし、支援者としてできることを模索しつつ、こどもぴあの活動と合わせて家族支援の重要性を広く伝えていきたいですね。
―― 縁の下で支えてくれる支援者がいることは、会に参加する方々にとって心強いと思います。それでは、小林さんはここで退室ですね。
(横山)そっか、小林さん、今日は本当にありがとうございました。がんばり屋さんなので、どうぞ無理されませんように。
(小林)ありがとうございます! それでは、私はここで失礼します。
―― では、ここからは横山先生お一人に、ケアラーにとって語り合いの場が果たす役割について、詳しくお聞きしていきます。
否定されない環境だからこそ、感情を解放できる
―― 家族のケア役割を担ってきた子どもたちにとって、語り合いの場がどのような役割を果たすのかについて、横山先生のご意見をお聞かせください。
一番大きいのは、安心できる場で、心の中に抱えていた思いや感情を外に出し、話せることだと思います。誰にも言えなかったことを言葉にしたとき、「わかる」「自分もそうだった」と仲間から共感してもらえると、それだけで心が軽くなりますよね。
また、他の人の話に共感するうちに、「自分だけがこんな気持ちを抱えていたわけじゃなかったんだ」と気づくこともあります。仲間の存在を知ることで、孤立感も軽減されますしね。語り合う機会を持ち続けることで、徐々に気持ちが整理され、消化されていくんだと思います。
―― やっぱり、自分の経験や気持ちを周りに話せていなかった方は多いですか?
そうですね、多いと思います。こどもぴあの参加者は若い方ばかりでなく、50〜60代の方もいて、涙ながらに「初めて人に話せた」とお話しされる方もいます。長い間、誰にも話せずに一人で抱えてこられたんだなぁ……と。
集いに参加して初めは「自分の感情がわからない」と悩む方も、回数を重ねるうちに、徐々に自分の感情を言葉にできるようになっていきます。例えば「辛くて苦しかった。親のことは許せない」と話していた方が、次第に「自分は親から愛されたかったのだろう」「親も病気を抱えていて辛かったんだと思う」と、親に対するさまざまな感情や思いに気づくんです。
また、自分の話をして周りから共感を得ることで、「自分の経験が誰かの役に立つ」と実感していきます。マイナスだと思っていた経験が、プラスに変わるんですよね。この体験を通じて、「過去の経験を活かして、同じ境遇の人の力になりたい」と前向きな気持ちが生まれる方も少なくありません。
―― 子ども同士だからこそ、発言を否定される心配がなく、安心して話せるのかもしれませんね。
周囲の人に自分の話をすると、「かわいそう」と過度に同情されたり、親を批判されたりすることもあるんですよね。でも、親を憎む気持ちがあったとしても、多くの子どもは親を愛している。だからこそ、自分の親を他人に批判されるのは、子どもにとって非常に辛いことなんだと思います。子どもたちの気持ちは、とても複雑。同じ立場の子ども同士だからこそ、否定されたり、批判されたりすることなく、安心して話せるんだろうなと思います。
あとは、「親は大切にするものだ」という社会の価値観に縛られて苦しんでいた方が、仲間と経験を分かち合う中で、「親の人生と自分の人生は別である。私は自分の人生を生きていいんだ」と気づくこともあります。
―― 社会の「親は大切にするもの」という風潮は、ケアラーの立場にいるからこそ、特に強く感じやすいように思います。
そうかもしれません。私の著書『静かなる変革者たち』の中でも、病気の母親のために福祉の支援者の道に進んだ方が、ご自身の体験を綴っていて。その方は、支援者になったことで気づくんですね。「家族は家族。家族の支援者にはなれない。家族だからこそ分かることもあるけど、家族には限界があり、面倒を見ることだけが家族の役割ではない」と。
家族を家族だけで支援しようとすると、結局、家庭内だけでぐるぐる回ってしまい、閉じた関係に留まってしまうんです。大事なのは、第三者に支援を任せること。そうすることで家庭が社会に開かれ、当事者の社会との関係も広がっていきます。
これは子どもだけでなく、親を含むすべての立場の家族に伝えたいことです。外部の支援を受けることで、家族それぞれが無理をせず、自分の人生を大切にしながら、家族関係を築き直していけるんだと思います。

(2025年3月こどもピアつどい開催時のスタッフ写真)
「孤独にならないように、仲間と繋がってほしい」
―― 家庭の問題を外に出すことは必要だと思いつつ、とても難しい課題だと感じます。第三者に助けを求めやすい社会をつくるためには、どうすればいいんでしょうか?
福祉制度の課題はまだまだ多いけど、まずは身近な人に気を配ることが、サポートの第一歩だと思います。あまり難しく考えなくてもいいんじゃないかな。
ケアラーの子どもたちを外から見ると、多くの課題を抱えているように見えるけど……。実は支援者が考えるサポートと、本人がほしいサポートは、必ずしも一致するわけではないんです。支援者の「なにかしてあげなきゃ!」という押し付けより、「あなたの話が聞きたい、理解したい」という、寄り添いの姿勢を求めている子どもが多いように感じますね。
例えば、母親の病気で家事や親のケアをしていることを初めて学校の先生に話したとき、「家の手伝いをしているなんて、えらいね!」と言われて、自分の気持ちを聞いてくれないことにガッカリした経験を持つ方もいて。「大人は誰もわかってくれないんだ」と、心を閉じてしまったそうなんです。やっぱり子どもたちは、周りの大人が子どもの目線で思いを聞いてくれることを望んでいるように思います。
―― 「えらいね、すごいね!」という言葉は、励ましのつもりでも、受け取る側は押し付けられた気持ちになるのかもしれませんね……。子どもたちの心を傷つけずに寄り添うためには、どうすればいいんでしょうか。
ヤングケアラーに関心を持つ支援者の方々は、子どもたちに対して本当にあつい思いを持っていると感じます。「助けたい、力になりたい!」という気持ちが私にも伝わってきますから。それはとても尊いことですが、支援の緊急性が高い場合もある一方で、支援者が「こうすべき」とアセスメントした支援が、子どもの思いとミスマッチになることもあるんですよね。
まずは、子ども自身の気持ちに耳を傾けて、信頼関係を築くことが大切だと思います。解決を急ぐのではなく、長期的に関わる意思を持つ。「なにかしてあげよう」と意気込むより、「いつも気にかけているよ」というメッセージを伝え続けることで、いざというときに、大人が差し伸べた手を子どもが取ってくれるんじゃないでしょうか。
―― その他、精神疾患の親を持つ子どもの立場の方や、ケアラー・元ケアラーの方々と関わる中で、横山先生が意識していることがあれば教えていただけますか?
親御さんと、敵対しないことかな。支援者の目にどう映っても、子どもにとっては「大好きなお母さん、お父さん」かもしれない。親と良好な関係が築けなければ、子どもとの信頼関係づくりも難しくなります。
親御さんと仲よくなることで、子どもたちの置かれている状況や感情がより深く見えてくることもありますからね。親と子ども、どちらも尊重しながら、親子をまるごとサポートしていくことが重要だと思います。
―― 最後に、子どもの立場の方々に向けて、メッセージをいただきたいです。
まずは「家族のケアをがんばっているね」と伝えたいです。家族のケアは決して悪いことではなく、その経験が子どもたちの力にもなっています。ただ、苦しくなったときは、「誰かに助けを求めたり、逃げたりしてもいいんだよ」とも、強く伝えたいですね。
ケアラーの子どもたちを見ていると、問題を抱え込んでしまう子が本当に多いです。子ども時代に信頼できる大人に出会えず、「一人でがんばらなきゃ」と思いながら大人になった人もいる。
だからこそ、孤独にならないように仲間と繋がって、自分の人生を歩んでほしいと願っています。これからも、こどもぴあのサポーターとして、こどもぴあが全国に広がる事を願い、ともに歩んでいきたいと思います。

プロフィール
横山 恵子(よこやま けいこ)
横浜創英大学 看護学部 精神看護学 教授/看護師
埼玉県立精神医療センター勤務後、急性期病棟で精神科看護を経験。その後、埼玉県立大学短期大学部看護学科講師、准教授を経て、埼玉県立大学教授に着任。現在は横浜創英大学教授を務めつつ、精神障害者家族会の活動に積極的に関わる。「精神疾患の親をもつ子どもの会(こどもぴあ)」設立も支援。著書に『精神障がいのある親に育てられた子どもの語り』、『静かなる変革者たち 精神障がいのある親に育てられ、成長して支援職に就いた子どもたちの語り』などがある。
- こどもぴあ公式HP:https://kodomoftf.amebaownd.com/
- 横山先生のおすすめ書籍:『私だけ年を取っているみたいだ。 ヤングケアラーの再生日記』水谷 緑(著)
ライター:くまのなな(@kmn_nana) カメラ:小林鮎奈