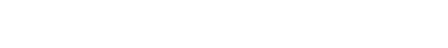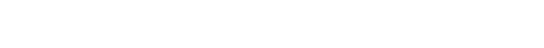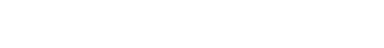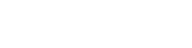ヤングケアラーに関わる方のネットワーク形成事業を実施しました

一般社団法人ヤングケアラー協会は、こども家庭庁補助事業「令和6年度 ヤングケアラー支援ネットワーク形成推進事業」を受託し、実施しました。(事業全体の実施レポートはこちらから)
ネットワークづくりの一環で、「わづくり〜ヤングケアラーが自分らしくいられる未来に向けて〜」を、大阪・北海道・東京・オンラインの計4回開催しました。わづくりは、民間支援団体、行政、福祉関連事業者、教育・医療関係者などのヤングケアラーを支える支援者やケア経験者などが参加し、多岐にわたる分野の関係者とのネットワーク形成を目的としたネットワーク構築を目的としています。
以下、わづくりの実施概要を簡単にレポートします。
| イベント詳細: |
【大阪会場】参加者:55名
| 開催日時:2024年 12月4日(水)15:00 ~ 17:30
開催場所:JAM BASE マルチスペース 登壇者(順不同) ・今井 紀明さん 認定NPO法人DxP 理事長 ・上村 文子さん 滋賀県ヤングケアラーコーディネーター ・宮崎 成悟 一般社団法人ヤングケアラー協会 代表理事 モデレーター:星野 桃代 一般社団法人ヤングケアラー協会 |
▼実施の様子
定員に近い参加者が参加し、関西地域の垣根を越えた交流や繋がりが生まれた。
<テーマ:新しいセーフティネットをつむぐ>以下、議論された主なトピックス
▼上村さんの活動
・地域と連携した夜の居場所づくりと、朝ごはんを食べられる環境づくりは、家族を支える子どもたちに安心できる空間を与える。
・18歳以上のYCとホップの収穫体験。単なる支援でなく出番と居場所をつくることを大事に。
・制度の仕組みを埋めるネジの役割。制度ではつながれなかった家族同士を、手間と時間がかかるオーダーメイドの支援で結びつける。
▼今井さんの活動
・LINEを使って匿名で簡単に相談できる「ユキサキチャット」の運用。13歳〜25歳の1万5000人ほどが登録しており、ヤングケアラーの当事者からの相談も。
・オンライン相談に来るこどもたちの6割は、支援制度を知らないか、知っていたとしても窓口に行くことに抵抗を感じるなどの状況。行政や地域の顔が見える支援環境も大切である。
▼大阪での交流会
ほとんどの方が2次会まで参加し、名刺交換をはじめ意見交換を実施。登壇者と話すだけでなく、参加者同士の横のつながり作りも多く見られ、会場の熱気が高まっていた。自身の活動や考えを共有し合い、新たなネットワークが形成された。その後、この繋がりから近畿地方の行政職員によるネットワーク会議も実施され、継続的な情報共有・意見交換の実施が期待される交流会となった。
<参加者アンケートより(抜粋)>
Q.本イベントを通して新たに得られた知識や情報はありましたか? [複数選択式]
他の支援者との交流・ネットワークを深めることができた…………………73.0%
支援の具体的なノウハウを学ぶことができた…………………………………….64.9%
最新の支援情報や知識を得ることができた………………………………………..43.2%
ヤングケアラー支援の新たなアイデアを知ることができた…………………32.4%
支援活動へのモチベーションを高めることができた…………………………..32.4%
今後の支援活動に役立つ情報源やツールを知ることができた………………35.1%
具体的な支援事例を知ることができた………………………………………………45.9%
ヤングケアラー支援の法制化や制度について理解を深めることができた..2.7%
自分の悩みや課題を共有することができた…………………………………………18.9%
特に得られることはなかった……………………………………………………………….0%

【北海道会場】参加者対面:26名 /オンライン視聴最大:56名
| 開催日時:2024年 12月11日(水)15:00 ~ 17:30
開催場所:北海道大学 オープンイノベーションハブ・エンレイソウ 登壇者(順不同) ・松田 考さん 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 こども若者支援担当部長/札幌市若者支援施設 統括責任者 ・池田 寛さん 苫小牧市健康こども部青少年課課長 ・加藤 高一郎さん 北海道ヤングケアラー相談サポートセンター センター長/一般社団法人 北海道ケアラーズ 代表理事 ・高岡 里衣さん 元ヤングケアラー モデレーター:宮崎 成悟 一般社団法人ヤングケアラー協会 代表理事 |
▼実施の様子
はじめてヤングケアラーに関わるイベントに参加するという方も見受けられ、交流会でははじめましてという声が多く聞くことになった。
<テーマ:若者ケアラーを支える仕組みと連携>以下、議論された主なトピックス
・解決を目指す安易なアドバイスよりも、ただ寄り添うことが大事なこともある。
・命のリスクはないが心配な子どものことを救える枠組みとして、協議会をうまく活用する。
・日本は相談窓口をつくりがち?居場所もつくりがち? 地域のフードコートなども居場所の社会資源になる。
・こどもケアラーは日常から離れられるようなキャンプやクリスマス会などが集いやすい。一方、若者ケアラーはただ楽しい時間を過ごすことに罪悪感を覚える場合もあり、例えばズボラ料理講座や適職診断など実益のある場の方が集いやすい。
▼北海道での交流会
ほとんどの参加者が、引き続き積極的に交流会に参加しました。登壇者の方々も、講演後に参加者と直接交流し、意見や考えを共有する姿が見られた。このような交流の場では、参加者と登壇者が互いに影響を与え合う、非常に有意義な時間となりました。登壇者も参加者からの質問やフィードバックを受けて、より深い議論や意見交換が繰り広げられていた。
<参加者アンケートより(抜粋)>
- 本イベントのご感想やヤングケアラー支援に関する疑問点、イベントを通して知ったこと、物足りなかった点や改善点など、お気づきのことをぜひお聞かせください。(自由記載)
・とても勉強になりました。ありがとうございます。参加者の皆さんのお話を聞いて、支援の難しさを改めて知ることができ、今後自分が何ができるかを考えるいい機会になりました。感謝です!
・ヤングケアラーという自覚をしていても苦しいと思わずに生活している子どもたちが多数いると思います(自分の役割と認識・納得していて)。そんな中で本当に「苦しい、大変」と思う子どもたちをどのように見つけるか?を支援者側として、関連団体と密に連携を取ることが大事だと思う。そのためには「ヤングケアラーとは?」という啓発活動の必要性が不可欠かと思う。
・大人として居場所づくりを考えるのでなく、子供たちが日常的に使ってるマック等を利用することもアイデアの1つは、目に鱗でした。
・はじめてヤングケアラー関連のイベントに参加しましたが、自分できることを形にしたいのでイベントを企画しようと思う時間でした。貴重なお話しと交流の場をありがとうございました。

【東京会場】参加者:52名
開催日時:2025年 2月19日(水)15:00 ~ 17:30開催場所:3×3 Lab Future登壇者(順不同)・こども家庭庁 支援局 虐待防止対策課・勝呂 ちひろさん 一般社団法人Omoshiro代表理事・幸重 忠孝さん 特定非営利活動法人こどもソーシャルワークセンター理事長・高岡 里衣さん 元ヤングケアラー・モデレーター:宮崎 成悟 一般社団法人ヤングケアラー協会 代表理事 |
▼実施の様子
東京会場では、市区町村の職員や関東エリアの支援団体、元当事者が参加。これからの支援の在り方など議論を深めていった。
<テーマ:多様な支援を根付かせていく>以下、議論された主なトピックス
▼勝呂さんの活動
・言葉はない会話はないかもしれないけれど一緒に散歩しててニコッと笑う瞬間を見せよう。親から繋がるのがomoshiroのやり方。
・こどもも親も誰も悪者にしたくない
・こどもが子どもらしくしていい時間は有限。その時間や景観が、自分の人生の舵を自分でとる感覚を育む
▼幸重さんの活動
・課題でこどもを振り分けない。
・YCだけを集めようとしても集まらない。学校や福祉(自治体など)から紹介してもらう。
・YCの声から事業を作っている。キャンプ、配食など。
▼クロストーク
・メディアが「頑張っているYC像」にスポットをあてることで、「自分ごときはYCでないと思った」と、YCを自認していた子を間違った方向に誘導しないように気をつけなくてはならない。
・当事者経験を語ることって慎重にならないといけない。ケアも病気も悪いことではないという発信の仕方が大切。
・「無料で勉強できるよ」は、こどもの気が向かないが、「お弁当配るよ」はこどもの親も嬉しい。
・残念ながら、企業がしたいことと、YCの願いに違いがある。そこの調整に専門性が必要。
・ボランティア:「何曜日に来たい」じゃなくて、このボランティアさんとサッカー少年と他の子を混ぜたら面白そうだ!をソーシャルワーカーとしてコーディネートすることが大事
・支援を受けずにいられる自分でありたい子がいることを忘れてはいけない。
▼東京での交流会
東京会場では、トンネル(タブロイド紙)で取材をさせていただいた方々が多数参加しており、参加者同士で紙面に関する質問が活発に交わされる場面が見受けられた。
また民間企業の参加も多く、支援先やこれからの支援の在り方の議論なども盛んに行われた。具体的には、支援の効果的な進め方や、より多くの人々に恩恵を届けるための方策について活発な議論が繰り広げられ、今後の支援活動に対する期待と関心の高さを感じられた。
<参加者アンケートより(抜粋)>
Q.新たにどのような活動(取組)を始めようと思いましたか?(自由記載)
・自治体に1人で若者支援担当兼務でYCCをしているので、新たに何か始めるのはキャパシティ的に困難です。やりたい気持ちはありますが…職務外の地元では楽しいものに肩書き関係なく参加したいです。
・ケアマネージャーを活用した支援体制
・ヤングケアラー支援の情報交換
・得られたネットワークを活用しつつ、自治体のヤングケアラー支援に寄与しようと考えています。
もともと、ヤングケアラーという言葉が浸透してきたので、さらにケアの種類を絞り込んで(高次脳機能障害)つながりをつくりたいと考えていて、さらにモチベーションが高まりました。
・民間企業と支援団体との新たな繋がりもできて、今後の展開が楽しみです。

【オンライン開場】参加者:105名
| 開催日時:2025年 3月5日(水)15:00~17:30
開催場所:オンライン(Zoom) 登壇者(順不同) ・【兵庫】神戸市こども・若者ケアラー相談・支援窓口 ・【福岡】福岡市ヤングケアラー相談窓口ヤングケアラーコーディネーター(特定非営利活動法人SOSこども村ジャパン)宮﨑 久美子さん ・【東京】一般社団法人ケアラーワークス 友田 智佳恵さん、氏原 拳汰さん ・モデレーター:宮崎 成悟(みやざき せいご)一般社団法人ヤングケアラー協会 代表理事 |
▼実施の様子
最大で102名の北海道から沖縄まで行政職員から支援団体、ヤングケアラーに関心があるという層まで幅広い参加者が参加。有意義な議論と交流を繰り広げらた。
<テーマ:聞いてみよう、全国のヤングケアラーコーディネーターの話>以下、議論された主なトピックス
▼神戸市の活動内容
・2019年の10月に市内で発生した20代の若者ケアラーの不幸な事件をきっかけに、全国に先駆けて行政直営の相談・支援窓口を設置(2021年9月)。
・相談経路の8割が関係機関。関係機関に対してのアプローチでYCの相談をつなげていくっていうことが必要だというのが分かってきている。
・高校生以上の当事者がオンラインで自分のしんどさなどを語る場を、NPO法人に委託し、2021年10月から月1開催。
・2022年の8月から訪問支援事業を行っているが、他人が家に来るというのを拒む傾向にあるようで、実績は伸びていない現状。
・兵庫県も2022年より窓口を立ち上げ、そのタイミングで弁当配布事業を開始し、好評。これをきっかけに接触率も伸びた。
▼福岡市の活動
・2021年11月に相談窓口設置。電話相談から訪問を行うことが多い。関係機関や支援団体等のパイプ役となっている。
・2023年度よりヤングケアラー支援ヘルパー事業を開始。
・社会的認知の向上のための活動、研修、ヤングケアラーが集まるサロンなども積極的に行っている。
▼ケアラーワークスの活動
・東京都府中市を拠点にヤングケアラー支援。運営者であるYC当事者の経験を活かし、ヤングケアラーズサークルという名前で、当事者同士が集えるコミュニティを運営。
・コミュニティ活動にYCが対面で参加しやすくするために、NPO法人日本トラベルヘルパー協会が無料で提供しているヤングケアラーを対象にしたヘルパーサービスをと連携している。サークルの活動費も無料。都内在住者に限り交通費も全額負担。
▼オンラインでの交流会
北は北海道から南は沖縄まで、全国各地から多くの参加者が参加。参加者は、行政の方々から民間団体、学校関係者やケア経験者の方など様々な職種で多様な視点が集まる場となった。ブレイクアウトルームでは、参加者が地域ごとに25のグループに分かれ、それぞれの地域の課題や取り組みについて意見を交わしていた。各グループでは、地域特有の問題に対する解決策や、地域間での支援のあり方について、さまざまな角度から議論が行われ、参加者たちは新たな発見を得たり、他地域の取り組みから学ぶ機会となった。
<参加者アンケートより(抜粋)>
Q.本イベントのご感想やヤングケアラー支援に関する疑問点、イベントを通して知ったこと、物足りなかった点や改善点など、お気づきのことをぜひお聞かせください。(自由記載)
・ヤングケアラーはこどもの権利侵害だという視点だったが、当事者の人の話からは事態の改善よりもわかってほしい気持ちが大きいのではないかと思った。困ってから相談するのではなく、大人や他者に気持ちを話す経験を通じて、相談して良い土壌をつくることができればよいと思った。
・構成内容も大変考えられており、学びと出会いの多い会でした。
・ネットワーキングの時間がもう少し長いと皆さんと満遍なく交流できたかなと感じました。
・当事者とその家族、気持ちまでしっかり寄り添う現場の意見を尊重した施策を構築していきたいと感じました。
・若い人達が沢山集まっていてまだ将来に希望があるな〜と思いました。
・「わづくり」のタイトルのとおり、ヤングケアラーへの支援の輪がどんどん広がっていることを実感しました。ヤングケアラーに関わる人たちが、それぞれの立場で活動し、つながり合い、連携を深めていくことで、輪が幾重にも重なっていくのだとあらためて感じました。
・今まで出会ったことのない地域の方々と交流ができて、大変有意義な時間でした。これからも繋がった方々と連携できるように連絡をしてみたいと思います。
ヤングケアラー支援ネットワーク推進事業は、例年に引き続き3回目の事業運営を実施しました。
<令和6年度ヤングケアラー支援ネットワーク推進事業全体の実施レポートはこちらから https://x.gd/FdIy6>

ヤングケアラー支援は、いま、大きな転換点を迎えています。
法制化が進み、これまで曖昧だった「ヤングケアラー」の存在が、社会の中でようやく認識され始めました。それにともない、子どもたちを支える支援者たちの声――「どう関わればいいのか」「どこまで介入していいのか」といった、具体的な悩みやニーズも、これまで以上に浮き彫りになってきています。
だからこそ今、私たち一人ひとりが「支援する人を支える」視点を持ち、つながりあうことが求められています。
学校、地域、福祉、医療、そして市民ひとり一人がネットワークを結び、子どもとその家族の暮らし全体を支える社会へ。それは「特別な人」が行うことではありません。あなたの声かけや気づきが、誰かの孤独をやわらげるかもしれません。
ヤングケアラーが「ひとりで抱え込まなくていい」と実感できる社会を、一緒につくっていきませんか?