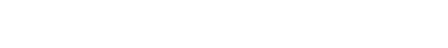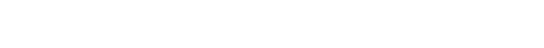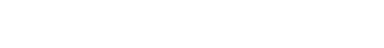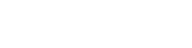ヤングケアラー協会の「LINE相談窓口」。ケアラーへの思いと、具体的な支援のかたち

病気の家族のケアや家事を担う「ヤングケアラー」。家庭を支える中で自分の時間が持てず、将来の選択に悩むことも少なくありません。18歳以上は「若者ケアラー」と呼ばれることも多く、成人となると責任や負担はさらに大きくなりがちです。
今回は、ケアラーとその家族を支援するヤングケアラー協会の小田桐麻未(おだぎり あさみ)さんにお話を伺います。小田桐さんは、協会の理事を務めながら、ケアラー向けのLINE相談窓口も担当しています(2025年3月現在)。窓口で相談できる内容や、家族を支える子どもたちへの思いについて、詳しくお聞きしました。
知識豊富な相談員が在籍。協会運営の「LINE相談窓口」
―― 小田桐さん、本日はよろしくお願いします。初めて伺いましたが、協会の事務所は東京都品川区の旗の台にあるんですね。
はい。二部屋あるうちの一つが、協会メンバーのオフィスです。今回使っているこちらの部屋は、ケアラーの方たちとの相談室にしたり、勉強スペースにしたり。家にいたくない子の避難所として、ここを解放することもあります。
キャリア相談の面談を、この部屋で行うこともありますね。本人の置かれている環境や性格、こちらとの関係性や信頼度に合わせて、柔軟に対応しています。

―― 本日はLINE相談窓口について、詳しくお聞きしたいと思っています。ただ、その前にヤングケアラー協会をご存じない方に向けて、協会の活動内容を教えていただけますか?
現在、協会の活動は3つに分かれています。
一つ目は、ケアラーの相談対応や直接的なサポート。LINE相談もこの活動に含まれています。LINE相談を通じて、さらに具体的な支援を希望される場合は、オンライン相談や対面の個別相談を実施することもあります。
二つ目は、仕組みづくり。ケアラーに支援を効果的に届けるため、どのような仕組みを作るべきかを考える活動です。自治体の障害福祉課や子ども家庭支援課などと協力して、よりよい支援体制を構築しています。これは「ヤングケアラーコーディネーター」と呼ばれる職種で、現在は特定の地域と連携しながら活動しています。
三つ目は、啓発活動。ケアラーの存在は徐々に認知されていますが、まだ十分ではありません。もっと多くの人に知ってもらい、ケアラーが抱えている問題について考えてもらうことが大切です。そのために、講演会や研修・メディア出演などを通じて、ケアラーの認知度を高める活動を行っています。
―― 協会の設立は2021年11月ですが、LINE相談がスタートしたのはいつ頃ですか?
LINE相談窓口を始めたのは、2022年7月ですかね。もともと埼玉県からご相談があり、ヤングケアラー協会も協力して、一緒に相談窓口を立ち上げることになったんです。
協会が設立されて間もない時期でしたが、協会の代表である宮崎が以前からケアラーのオンラインサロンやコミュニティ運営を積極的に行っていたので、その実績を評価していただけたと感じています。
現在は埼玉県以外の地域とも連携し、各地の相談窓口を運営させてもらっています。また、自主事業として、全国対象のヤングケアラーのキャリア相談窓口も運用しています。
―― 協会側も、LINE相談窓口の開設は初めての試みだったんですよね。スタートにあたり、ご苦労はありませんでしたか?
相談窓口の開設当初はすべて手探りだったので、大変ではありました。ただ、私自身が、この相談窓口をやりたいと思っていたので。忙しくても、まったく苦には感じませんでした。
現在は相談員の数も増え、障害者向け支援施設の経験がある人や、ユースワーク(若者の成長を支援する活動や考え方)に精通している人など、異なる専門性を持つ相談員が在籍しています。私自身も相談員の統括をしながら、現在も現場で活動を続けています。
―― 小田桐さんが「相談窓口をやりたかった」と思っていた理由を聞いてもいいですか?
一番の理由は、私自身が元ヤングケアラーで、現在も若者ケアラーだからかな。母がうつ病などの精神疾患をいくつか併発していて、学生の頃から家事や母親のケアをしていました。母子家庭だったので、アルバイトをして経済的にも家庭を支えていたんです。振り返ると、大変なことも多かったけど……。年を重ねるごとに「自分は運がよかった」と感じるようになりました。
高校の担任の先生が気にかけてくれたり、大学のゼミの教授が理解を示してくれたり。社会人になってからも、ケアに理解のある会社で働くことができました。支えてくれる大人たちがいたからこそ、こうして自分の人生を生きられているような気がします。当時の自分のように、困難を抱えるケアラーに対して、今度は私がなにかできたらと思っています。
会社員時代は人事の経験を積み、キャリア相談を受けることにやりがいを感じていました。キャリアコンサルタントの国家資格も持っているので、これまでの経験や知識を活かしながら、LINE相談を通じて私ができる支援を届けたいと考えています。
「LINE相談は、ブロックされたら終わり」
―― 窓口には、実際にどのような悩みが届きますか? プライバシーの問題もあると思うので、答えられる範囲で教えていただきたいです。
個人に寄りすぎず、抽象的に分類してみますね。小中高生の悩みとしては、学校と家庭の両立に関するものが多いです。「家事や家族のお世話に追われて部活ができない、友達と遊べない」「親のケアに時間を取られて勉強が進まない」といった相談がよくあります。
もう少し年齢が上がると、増えてくるのは進学や就労の悩み。「大学進学のお金がない」「家を離れて就職する未来が見えない」「親のケアをしながら働けるのか不安」などです。
さらに年齢を重ねると、仕事とケアの両立の悩みが増えてきます。「家に給料を入れているので、自分のお金がない」「親のケアで仕事を休まないといけない」など、仕事と家庭の間で板挟みになっているケースが多く見られます。
また、そもそも「家族のケアをしていたら就職ができないまま年を重ねてしまった」というお悩みも非常に多いです。
あとは、30代以上の方から「辛かった過去の記憶が消えない」「部活や恋愛、結婚やキャリアアップなど、ケアに追われて周りが経験していることができていない自分に不安を感じる」といったSOSが届くこともありますね……。

―― それぞれの悩みに対して、どのようにサポートしているのかお聞きしたいです。まずは、小学生・中学生・高校生の子どもたちへは、どのように働きかけていますか?
子どもたちへの支援は、正直とても難しいです。特に小中学生からのLINE相談は、どうしても情報量が少なくなりがち。こちらが知りたい部分まで聞き取れないことも多いので、自分たちも話し相手として繋がりつつ、可能な限り地域の支援者にも繋げるようにしています。
例えば、学校のスクールカウンセラーや地域の子ども家庭支援課など。事前にそうしたセクションの方たちとこちらもお話しした上で、「あなたが住んでいる地域に、こういう相談員さんがいます。何曜日の何時からお話しできるみたいだけど、会ってみない?」といった形でアプローチします。
―― 支援者と繋ぐ際に、子どもから拒否反応が出ることはないんでしょうか? 「クローズドなLINE相談の場」から、「支援者と会うオープンな場」へ移ることへの抵抗感というか……。
そうですね、ありますね……。感覚的には、メッセージを送ってくれる7割くらいの子が、最初は私たち相談員を警戒しています。「どこかに通報されるかも」と心配したり、「親に伝わったらどうしよう」と不安を感じていたり。
ただ、知らない大人に警戒心を持つのは自然なこと。だからこそ、まずは私たち相談員との信頼関係を築くことが大切です。最初のアプローチで支援者との対面を拒否されたとしても、諦めずに関係を続けていれば、二度目、三度目の打診で気持ちが変わることもあるんですよ。
―― 警戒心を持つ子に対して、すぐに距離を縮めないようにしているんですね。
そうです。支援者側は「すぐに助けなきゃ、適切なところと繋げなきゃ!」と考えがちですが、その善意がかえって逆効果になることも多いんですよね。LINE相談は、相談のハードルが低い分、去るハードルも低い。こちらとしては、ブロックされたら終わりです。
重要なのは、本人が納得して、自分のタイミングで支援を受けること。そのためにも、焦らずに信頼関係を築くことを常に意識しています。
―― 続いて、進学や就労の悩みについては、どのようにサポートしていますか?
小学生や中学生の相談は心の寄り添いが中心ですが、進学や就労に関する悩みは、より具体的なアクションが求められます。まずは全体像を具体的に把握する必要があるので、Zoomなどを活用して直接お話をすることが多いかな。
現在の学力や希望する業界・職種、家庭環境など、さまざまな要素をヒアリングしたうえで選択肢を提示して、進むべき道を一緒に探っています。一方的にアドバイスをしても、最終的には本人が納得しないと意味がないので……。「あなたはどうしたい?」と問いかけて、本人の気持ちを尊重することを心がけています。
とはいえ、ケアラーの方は自分軸で生活できていないことが多く、「自分がどうしたいのか」があまり浮かばないケースがよくあります。だからこそ、まずは選択肢を知った上で考えてもらう、というステップを大切にしています。

―― ちなみに、オンライン相談も、無料で利用できますか?
もちろんです! オンライン相談も含めて、すべての相談は無料で提供しています。
―― それは心強いです。では、仕事とケアの両立については、どのように対応していますか?
まずは状況を整理して、使えそうなサービスを探します。家事をサポートしてくれるNPOやボランティア団体はないか、未申請の福祉制度はないか。利用できるサービスがあれば、申請の手続きまでこちらで手助けします。
また、先述の通り、社会人の年齢の方だと「家族のケアで職歴がない。今から働ける?」と悩んでいる方も多くて……。周りが経験済みのことを聞くのが恥ずかしく、就活の基本的な情報すら得られていない場合もあります。勇気を出してハローワークに行っても、就活の知識がある前提で話が進んでしまうことも珍しくないんですよ。
協会では、安心して相談してもらえるように、できるだけ基礎から説明しています。ときには正規雇用と非正規雇用の違いや、面接の流れ、履歴書の書き方を教えることも。さまざまな情報を伝えたうえで、相談者が自分に合った選択をできるようサポートしています。
―― 続いて、元ケアラーの方たちが抱える「辛い気持ちが消えない」「ケアに追われて周りが経験していることができていない」という悩みには、どのようにサポートされていますか?
基本的には、本人の話を傾聴するよう意識しています。無理に踏み込みすぎると、本人が開けたくない心の蓋まで開けてしまう恐れがあるので、バランスを見ながら、本人の気持ちが落ち着くよう心がけています。
できなかった経験がある過去は、変えることができないと思っています。でもその分、他の経験を積んできたとも言えると思うんです。
だからこそ、客観的に「今までがんばってきたんですね」と伝え、努力に対してプラスの意味づけをすることを心がけています。周りと経験の違いがあっても、本人の努力や人生には絶対に価値がありますから。
返信が途切れることもありますが、無理に催促はしません。メッセージのやり取りを義務として捉えず、心が揺らいだときの逃げ場所としてLINE相談を利用してもらえることが、私たちが提供したい理想の形だと考えています。
「正論は届かない」相手に寄り添う姿勢が大切
―― 今後もLINE相談窓口を続けていく中で、なにか改善したい点はありますか?
現在も知識や経験を持つ人のみで活動していますが、まだ足りない部分があると感じています。例えば、精神疾患の治療に詳しい専門家や、発達特性や知的障害に関する知識を持つ人がいれば、さらに幅広い相談に対応できるはず。
知識を持つ人を新たに招くのか、既存メンバーの知識を増やすのか……。今後の協会の課題として、真摯に取り組んでいきたいですね。
―― 支援者としてケアラーと関わる中で、小田桐さんが気をつけていることを教えてください。
ケアラーの方たちに、正論をぶつけないように意識しています。「生活保護を申請したほうがいい」「今のやり方では限界がある」などの正論をすぐに言いたくなる場面も、実際にあるんです。でも、相手の希望や本心を無視して正論を言っても、結局はなにも届かないんですよね。
家族のケアをしている方にとって、そのときの状況は、自分にできる最大限の努力の結果。その努力を認めないと、相手はこちらを拒否するだけです。自分の経験や知識だけで判断せず、目の前の方に合わせて必要なサポートを考える姿勢が、支援者には求められると思います。
―― 最後に、ケアラーの方たちに向けて、なにか伝えたいことはありますか?
「本当にがんばってるね」と、まずは伝えたいです。自分がしてきたことを、なにより自分自身で認めてほしい。家族のケアや家事を「しんどい」と感じることに罪悪感を持つ子も多いけど、それに対しても「しんどいと思っていいし、逃げてもいいんだよ」と言いたいです。
―― 周りからの「逃げてもいい」の言葉は、家族を支えるケアラーにとって、人生の選択肢を広げるきっかけになりそうです。
私自身、母のケアをしていた高校時代、先生の言葉でハッとしたことがあるんです。母を優先して進路を決めようとしていたとき、先生に「たぶん、お母さんのほうが先に亡くなるよ。自分の人生をお母さんに捧げて、一人になったとき、お母さんを恨まない?」と言われて。

衝撃でしたね。自分が支援者としてこの言葉を使うかはわからないけど、同情ではなく事実を伝えてくれたおかげで、「母のことが好きで、支えたいと思う気持ちが本心でも、母の人生と私の人生は別なんだ」と気づけました。
私は神様ではないので、私の言葉で誰かの人生を大きく変えることはできないだろうと思っています。でも、できる限り一人ひとりの状況に合わせて私たちができることをし続けていくことで、小さくてもいいから、いい波紋を生み出せたらいいなと思っています。
プロフィール
小田桐 麻未(おだぎり あさみ)
1991年生まれ、北海道出身。元ヤングケアラーで、現在は若者ケアラー。北海道大学を卒業後、ITベンチャー企業で人事に従事。国家資格キャリアコンサルタントおよびメンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種を取得。退職後はフリーのコーチとして活動。「ケアラーが自分の興味や適性に合ったキャリアを築き、納得のいく人生を歩めるように」との思いから、ヤングケアラー協会に参画。協会の理事を務めながら、LINE相談窓口の統括としても活躍している。
ヤングケアラー協会公式HP:https://youngcarerjapan.com/
ライター・カメラ:くまのなな(@kmn_nana)