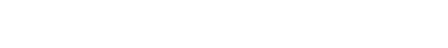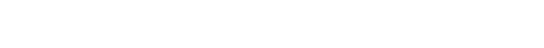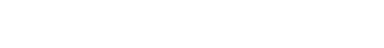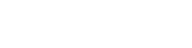【全国】ケアラー・ヤングケアラー支援条例の一覧と解説

1.はじめに
2.ケアラー支援条例とは
3.全国でも特徴的な条例をご紹介
4.条例の制定状況一覧:全国で32の条例が制定(2025年3月27日現在)
5.なぜ条例の制定が進んだの?
6.おわりに
7.参考資料
1.はじめに
現在、ヤングケアラーの支援に向け、様々な側面から状況の整備が進められており、そのひとつとして法的な環境整備があります。
代表的な例として、埼玉県は令和4(2022)年に全国初となる「埼玉県ケアラー支援条例」を制定し、その中でヤングケアラーについても明記しました。その後、全国の地方自治体でも、ケアラーやヤングケアラーの支援に関する条例が制定される機運が高まっています。最近では、秋田県でも議会の全会一致により秋田県ケアラー条例が可決されました。
また、条例より上位の法体系である国の法律でも、ヤングケアラーが定義されたことはまだ記憶に新しい出来事です。令和6(2024)年6月にヤングケアラーの定義を初めて法律に明記した「改正子ども・若者育成支援推進法(子若法)」が成立しました。
2.ケアラー支援条例とは
⑴目的・概要
地方公共団体で制定されているヤングケアラーやケアラーに関する条例は、主に以下のような趣旨で定められています。
・ケアラーを地域社会全体で支えること
・ケアラーの支援に関し、基本理念を定め、地方公共団体の責務並びに町民、事業者及び関係機関の役割を明らかにすること
・ケアラーの支援に関する施策の総合的、計画的な推進を図ることにより、ケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現すること

3.全国でも特徴的な条例をご紹介
2025年3月27日現在、全国の地方自治体では計32 の条例が制定されています。特徴的な条例をピックアップしてご紹介します。
①鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり推進条例
出典:https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00002019.html
この条例で特徴的なのは、ケアラーやヤングケアラーだけではなく、産後うつ、老老介護、8050問題など、家庭内に生じる孤独や孤立に目を向けていることです。
「家庭内における過重な介護等の負担により学習や就業に支障を来しているヤングケアラーといわれる若者、子育てにおける孤立感等が原因となる産後鬱を発症する者、高齢者が高齢者を介護する老老介護や高齢の親が中高年のひきこもり状態にある子を支える8050問題といわれる身体的又は精神的負担を負う者等が、本人が望まない孤独を感じ、又は孤立していることが、大きな課題として認識されるようになった」(前文)
として、核家族化の進行、都市化の進展、社会の高度化・複雑化などの家庭を取り巻く環境の変化に伴って起こる家庭内の課題に対して、本人や家庭に頼るのではなく、周囲の理解や協力を得ながら、県民それぞれの生活の実情に即した、きめ細やかな対策が必要としています。
②京都市ケアラーに対する支援の推進に関する条例
出典:https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/img/news/R06/061106carer4.pdf
この条例で特徴的な点は、京都市内でのケアとケアを担うケアラーに関わる先駆的な事業や活動が展開され、根付いてきた歴史を踏まえている点です。
京都市には、
・1879年に日本最初の公立盲学校・聾唖学校として府立盲唖院が開校した
・1980年に「呆け老人をかかえる家族の会」として、日本初の認知症の家族会が設立した
・日本における精神病者のための最初の施設として、京都岩倉の紫雲山大雲寺があるほか、1875年に最初の医療施設として京都市南禅寺に公立精神病院・京都癲狂院が開設された(黒木,2017)
など、ケアに関わる場所や歴史が多く存在しています。
さまざまなケアとともに歩んできた地域であるからこそ、基本理念として、ケアラーの多様性への配慮が示されているのでしょう。
また、ケアラーの定義に「使用する言語等により援助を必要とする親族などをケアする者」を加えたのは、京都が初めて。支援施策の実施については、「必要な財政上の措置を講じる」と定めており、努力義務よりも踏み込んだ内容で作成されていることも特徴的です。
③ケアをされる人もする人も自分らしい生き方ができる藤沢づくり条例
出典:https://shigikai.city.fujisawa.kanagawa.jp/voices/GikaiDoc/attach/Shiryo3/Sr3B201_jyourei1.pdf
「人は、みな誰かから身体や心のケアをされて生きています」から始まる神奈川県藤沢市の条例は、ケアの大切さを示す内容が特徴的です。「ケアをされる人もケアをする人もどちらもが大切にされ、夢と希望を持って健康で文化的な自分らしい人生を送ることができるよう、社会の仕組みを整えていくことが必要です」と述べ、ケアをされる人とケアをする人の声や望を政策に反映することを目指し、条例を制定しています。
条例案や政策案に対し、本会議や委員会とは別に全会派で話し合う場となる「政策検討会議」を設置し、提案のしやすさや議論の活発化のための設置要綱を定めたことは、「第19回マニフェスト大賞」の議会改革部門優秀賞を受賞しています。条例に関してもこの仕組みで議論が重ねられ、条例の制定に至りました。

4. 条例の制定状況一覧:全国で32の条例が制定(2025年3月27日現在)
| 自治体 | 条例名 | 施行日 | 条例URL |
| 埼玉県 | 埼玉県ケアラー支援条例 | 令和2年3月31日 | 埼玉県ケアラー支援条例 |
| 北海道栗山町 | 栗山町ケアラー支援条例 | 令和4年4月1日 | 栗山町ケアラー支援条例 |
| 三重県名張市 | 名張市ケアラー支援の推進に関する条例 | 令和3年6月30日 | 名張市ケアラー支援の推進に関する条例 |
| 岡山県総社市 | 総社市ケアラー支援の推進に関する条例 | 令和3年9月9日 | 総社市ケアラー支援の推進に関する条例 |
| 茨城県 | 茨城県ケアラー・ヤングケアラーを支援し、 共に生きやすい社会を実現するための条例 |
令和3年12月14日 | 茨城県ケアラー・ヤングケアラーを支援し、 共に生きやすい社会を実現するための条例 |
| 北海道浦河町 | 浦河町ケアラー基本条例 | 令和3年12月14日 | 浦河町ケアラー基本条例 |
| 岡山県備前市 | 備前市ケアラー支援の推進に関する条例 | 令和3年12月24日 | 備前市ケアラー支援の推進に関する条例 |
| 栃木県那須町 | 那須町ケアラー支援条例 | 令和4年3月14日 | 那須町ケアラー支援条例 |
| 北海道 | 北海道ケアラー支援条例 | 令和4年4月1日 | 北海道ケアラー支援条例 |
| 埼玉県入間市 | 入間市ヤングケアラー支援条例 | 令和4年7月1日 | 入間市ヤングケアラー支援条例 |
| さいたま市 | さいたま市ケアラー支援条例 | 令和4年7月1日 | さいたま市ケアラー支援条例 |
| 福島県白河市 | 白河市ケアラー支援の推進に関する条例 | 令和4年9月30日 | 白河市ケアラー支援の推進に関する条例 |
| 長崎県 | 長崎県ケアラー支援条例 | 令和5年4月1日 | 長崎県ケアラー支援条例 |
| 鳥取県 | 鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり推進条例 | 令和5年1月1日 | 鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり推進条例 |
| 奈良県大和郡山市 | 大和郡山市ケアラー支援条例 | 令和5年4月1日 | 大和郡山市ケアラー支援条例 |
| 栃木県 | 栃木県ケアラー支援条例 | 令和5年4月1日 | 栃木県ケアラー支援条例 |
| 栃木県鹿沼市 | 鹿沼市ヤングケアラー支援条例 | 令和5年4月1日 | 鹿沼市ヤングケアラー支援条例 |
| 埼玉県戸田市 | 戸田市ケアラー支援条例 | 令和5年4月1日 | 戸田市ケアラー支援条例 |
| 埼玉県上尾市 | 上尾市子ども・若者ケアラー支援の推進に関する条例 | 令和5年7月1日 | 上尾市子ども・若者ケアラー支援の推進に関する条例 |
| 福島県本宮市 | 本宮市子ども・若者ケアラー支援の推進に関する条例 | 令和5年12月14日 | 本宮市子ども・若者ケアラー支援の推進に関する条例 |
| 北海道むかわ町 | むかわ町ケアラー支援条例 | 令和6年4月1日 | むかわ町ケアラー支援条例 |
| 福岡県みやこ町 | みやこ町ケアラー支援条例 | 令和6年4月1日 | みやこ町ケアラー支援条例 |
| 北海道秩父別町 | 秩父別町ケアラー基本条例 | 令和6年4月1日 | 秩父別町ケアラー基本条例 |
| 北海道恵庭市 | 恵庭市ケアラー支援条例 | 令和6年4月1日 | 恵庭市ケアラー支援条例 |
| 群馬県安中市 | 安中市ヤングケアラー支援条例 | 令和6年4月1日 | 安中市ヤングケアラー支援条例 |
| 熊本県合志市 | 合志市ヤングケアラー支援条例 | 令和6年4月1日 | 合志市ヤングケアラー支援条例 |
| 埼玉県蕨市 | 蕨市ヤングケアラー支援条例 | 令和6年3月21日 | 蕨市ヤングケアラー支援条例 |
| 北海道苫小牧市 | 苫小牧市ヤングケアラー支援条例 | 令和6年4月1日 | 苫小牧市ヤングケアラー支援条例 |
| 岐阜県 | 岐阜県ケアラー支援条例 | 令和6年4月1日 | 岐阜県ケアラー支援条例 |
| 神奈川県鎌倉市 | 鎌倉市ケアラー支援条例 | 令和6年4月1日 | 鎌倉市ケアラー支援条例 |
| 京都市 | 京都市ケアラーに対する支援の推進に関する条例 高齢 | 令和6年11月11日 | |
| 神奈川県藤沢市 | ケアをされる人もする人も自分らしい生き方ができる 藤沢づくり条例 |
令和7年4月1日 |
(2025年3月27日時点での情報を掲載しています。今後情報を更新していきます)
5.なぜ条例の制定が進んだの?
全国で初めて制定された「埼玉県ケアラー支援条例」の制定の経緯について、当時の埼玉県地域包括ケア課がこのようにコメントをしています。
「埼玉県は、少し前まで『(年齢が)若い県』と言われていたんです。でも、ここ5年ほどで、全国でもトップクラスのスピードで75歳以上の後期高齢者の方が急増しています。そして、条例ができる以前の2016年頃から『(ケアが必要な)高齢者の方が増えるなら、ケアする人の数も負担も増える。ヤングケアラーと呼ばれる子どもたちも含め、これは今後絶対にケアラーの支援が必要になる』と感じるようになり、ケアする側の人々を対象にした支援やサポートが検討されはじめたんです。
具体的な動きとしては、ケアラー支援の必要性を訴えていた民間団体の方々にお話を聞いたり、2017年から地域包括支援センターの職員向けの研修を行ったりしました。埼玉県議会の県議団の皆さんがプロジェクトチームを作って、検討を重ねたりもしました。そんな流れがあったからこそ、条例の制定に繋がったのだと思います」
地方公共団体で条例が制定されたことによる影響は大きく、埼玉県でのケアラー支援条例の制定を受け、他の地方公共団体でもケアラー支援条例が制定されるようになりました。例えば、長崎県では、「埼玉県の取り組みに追随する形で(中略)、長崎県にも新たな視点によるケアラー支援に係る取り組みが求められている状況」を背景として、「長崎県ケアラー支援条例」を制定しています。このように、ひとつの自治体の取り組みが、今現在まで影響を与え続けています。
6.おわりに
ヤングケアラーやケアラー支援のための条例は、様々な地方公共団体で制定されています。条例の内容や制定までの背景を調べる過程で、条例の制定に関して、ケアに対しての色々な思いや願いを持った人々の姿が垣間見えました。
埼玉県の条例が制定されてから5年がたち、ケアを取り巻く環境も徐々に変化しています。国の法律はもちろんですが、家族とともに暮らす地域でケアラー支援条例が制定されることで、ケアを必要とする家族やケアラーがさらに安心して暮らせる地域へとつながっていくでしょう。法律とともに、それぞれの地域の実情やニーズに合わせて、ケアとともに生きる私たちの生活をそっと照らしてくれることを願っています。
7.参考資料
ヤングケアラーを初めて定義 改正子ども・若者育成支援推進法が成立-福祉新聞Web
ケアラー支援に関する条例 | 法制執務支援 | 条例の動き
明治期における精神看護の礎 The Foundation of Mental Care in the Meiji Era
京都市ケアラー条例 市民と議員一体で制定 市民団体が公開学習会
藤沢市議会「改革推進会議」 マニフェスト大賞 優秀賞に 討議の活発化評価
埼玉県すごくね?国に先がけ全数調査 見えた本音 ヤングケアラー調査隊
長崎県ケアラー支援条例 【逐条解説】
執筆:横川あゆみ